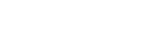教育
「QYワークショップ」の成果報告会を横浜国立大学で実施しました
2025年2月17日、経済学部池島ゼミと情報サービス会社QUICKは「QYワークショップ」の成果報告会を横浜国立大学で実施しました。QYワークショップは2023年度から始まった取り組みです。今回は今年度の成果報告をかねたワークショップを実施しました。
2023年度に訪問した珠洲市をおそった地震被害を考慮しつつも、現地への再訪は難しいと判断し、2024年度は他地域を調査対象としてきました。2024年11月には金沢市を会場にワークショップを開催しましたが、後日、学生は現地へのヒアリング調査やアンケート調査を実施して
学生による成果発表では、まず「地域の衰退とはなにか」について議論されました。衰退を①人口減少、②経済活動の停滞、③インフラの縮小から捉え、それぞれの具体的な状況が述べられました。地域経済の課題として頻繁に取り上げられる人口や経済活動の縮小だけでなく、インフラの縮小を捉えることで、衰退している地域の実態についてより深く迫った分析結果が発表されました。さらに、この3つの衰退がさらなる衰退をもたらす負の連鎖に言及し、地域経済循環の考えが衰退を止める鍵となりうるという結論に至りました。
続く発表では、地域まちづくり会社による経済循環の構築について発表がありました。具体例として宮城県石巻市の水産加工業や石川県輪島市の株式会社御祓川の取り組みが紹介されました。これらの事例を通じて、外部からの資金流入の重要性が強調され、地域経済循環にもたらす効果やその課題について議論が行われました。また、急激な需要増大が事業運営者の負担になり店舗運営が停止する可能性が、ヒアリングから明らかになったと述べられました。これを基に、外部からの資金流入が多ければ良いわけではなく、持続可能な事業運営も重要であるという結論に至りました。
最後に、禅の里交流館管理部長の宮下氏にご協力いただいた、輪島市でのアンケート調査の結果をもとに、贈与経済の役割について研究が発表されました。まず、贈与経済とは何か、そしてその役割に関する研究が紹介されました。次に、アンケートの結果明らかとなった、贈与の頻度や始まった時期、理由など、輪島市における贈与の実態について多角的な視点から発表がされました。特に、贈与が世代を超えて相互的に行われていることや、贈与を通じた社会的絆の強化が確認されました。これを通じ、贈与がつくるコミュニティが地域の衰退を食い止める可能性が提起されました。
2024年11月のワークショップ![]() で、地域住民や企業の方々から直接話を聞いたことで学生たちは広い視野を取り入れ、かつその際に出会った皆様に協力いただいたことで、今年度の有意義な調査分析を行うことができました。また、学生はプロジェクトを通して過去研究の調査やヒアリング、データ収集を行ったことで、大きな成長と学びの機会となりました。
で、地域住民や企業の方々から直接話を聞いたことで学生たちは広い視野を取り入れ、かつその際に出会った皆様に協力いただいたことで、今年度の有意義な調査分析を行うことができました。また、学生はプロジェクトを通して過去研究の調査やヒアリング、データ収集を行ったことで、大きな成長と学びの機会となりました。

また、高崎商科大学の梅村教授から、学生の発表に対するコメントや未観測経済に関して講演していただきました。未観測経済は統計に現れないさまざまな経済活動を含んでおり、生活視点からその重要性が再確認されました。島根県や石川県、高知県などの事例から新たな地域振興のあり方が紹介され、参加者にとって新しい視点が提供されました。
本学の池島教授からは、未観測経済を統計制度から整理するとともに、ご自身がこれまで取り組まれてきた「可視化」に関する講演がありました。伝統野菜の遺伝子が持つ経済的価値に関する研究や食の循環と環境負荷に関する研究など、未観測だった経済の側面を取り扱った研究が紹介され、未観測経済へのアプローチを学ぶ機会となりました。

最後にはQUICK北村氏と梅村教授、池島教授が登壇し、パネルディスカッションを行いました。「身近にある未観測経済」「未観測経済への接近アプローチ」といったテーマで参加者が積極的に意見を出し、その意見をふまえて登壇者が意見交換を進めました。特に、どのようにデータを集めるかについて活発に議論が行われました。未観測経済において、政府統計では調査対象とならないデータを集めるため、研究者が自らデータを集める必要があり、現地に訪問することやデータの保有者と信頼関係を築いていくことの重要性が梅村教授と池島教授から語られました。また、現地調査の経験が豊富な梅村教授から、過疎地での贈与経済の現状や地域住民主体で行われている祭り等様々な取り組みについて、未観測経済という視点からお話しいただきました。実際に研究するにあたって、問いの立て方や分析の進め方をお話しいただき、学生はより深い学びの機会となりました。
今回のワークショップを通じて、地域経済循環や未観測経済についての理解が深められました。具体的な事例や研究方法の紹介もあり、今後の研究や実践に役立つ視点が多く提供されたと言えます。
また、一連のワークショップと調査の実施にあたり、株式会社QUICKや石川県の地元企業や地域住民の皆様など多くの方々から多大なるご支援とご協力をいただきました。ワークショップの開催にご協力いただいたすべての皆様に深く感謝申し上げます。