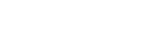教育
学生との新しい挑戦!
日本の経済統計データを集約したウェブサイトを構築【相馬尚人准教授】
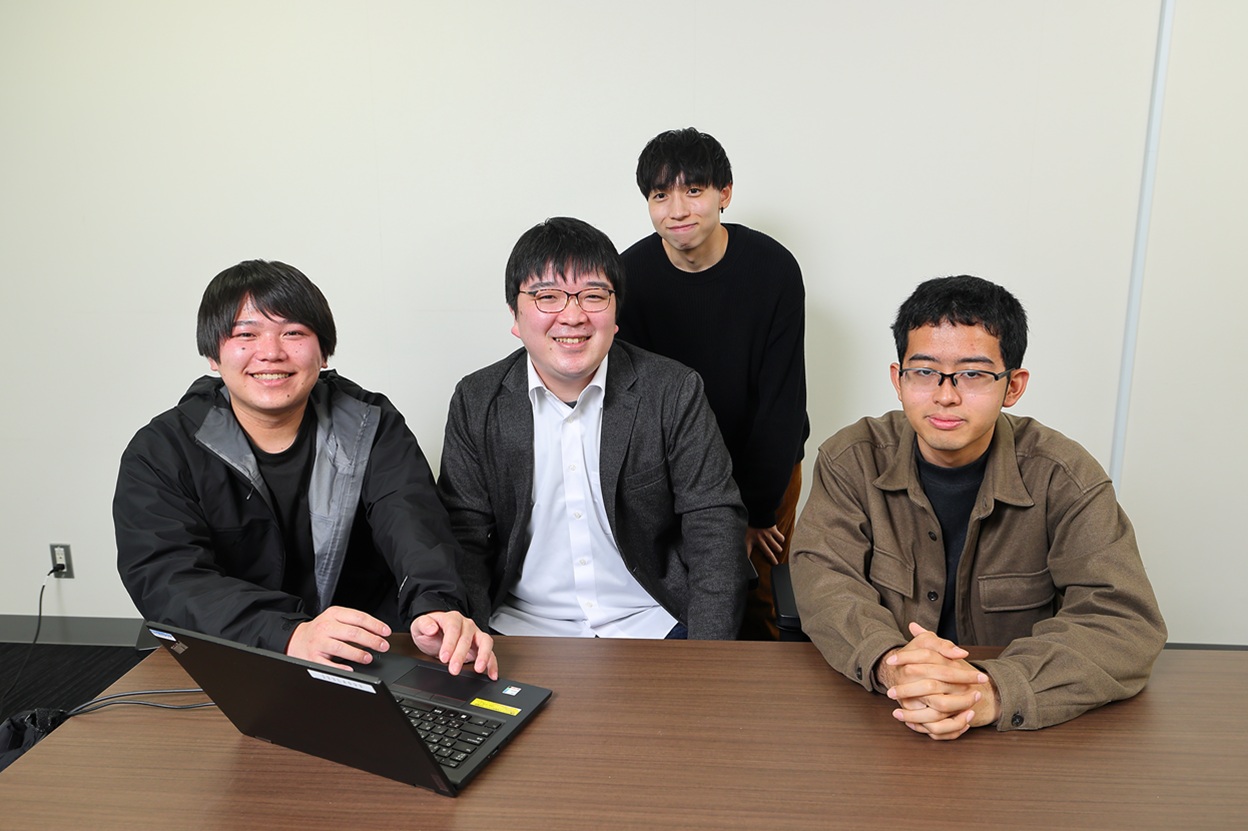
日々、様々な日本経済の統計データが発表されている。ところが、データはあるものの、それを分かりやすく見せたり、比較したりできるサイトはほとんど存在しない。そこで「ないなら自分たちで作ってしまえ」と号令を発した相馬尚人先生主導のもと、2025年春の公開を目指して日本の経済統計データを集約したサイトの構築が進んでいる。
目次
- 経済学におけるデータサイエンスの意義とは?
- 日本国内の統計データを集約したサイトの必要性
- 余計な労力をかけず、「もっと使いやすく!」を実現させる
- 厳しい?指摘の連続で、サイトはどんどん充実!
- 横浜国立大学経済学部を志望する皆さんへ
経済学におけるデータサイエンスの意義とは?
相馬尚人先生の専門分野はマクロ経済学。「日本の景気はどうなるのか」「経済成長を続けて行けるのか」など、いわゆる経済学としてイメージされる学問がマクロ経済学だ。
「マクロ経済学では昔から当たり前のようにデータが使われてきました。現実のデータから情報を得て、それを経済の理論に活かしたり、その理論の検証にも実際のデータが用いられます。この営みに新しくついた名前がデータサイエンスという認識です」と相馬先生。
加えて、少し前まではデータとして考えられていなかったテキスト情報なども処理対象として活用されるようになった。「例えば政府や中央銀行が出す公式文書には政策の意図や具体的な政策内容が書かれていますが、それは基本的に人が読み取るもので、統計的に扱えるデータではありませんでした。しかし、技術の発展によってデータとして処理できるようになっただけでなく、従来のデータよりもリアルタイムかつ正確な経済情報が得られるようになりました。これはデータサイエンスがマクロ経済学にもたらした恩恵だといえます」

国内の経済統計データを集約したサイトの必要性
アメリカの中央銀行が1991年から運営しているFRED(Federal Reserve Economic Data)というWebサイトがある。ここにはアメリカを中心に各国のマクロ経済データがまとめられており、GDPや失業率などの指標をもとに見やすく図示してくれる。グラフの拡大・縮小などの操作も直感的で使い勝手がよく、必要な経済データを入手する際に重宝するという。
「ところが日本には、このレベルのサイトが一切ありません。そのため、日本経済のことを紹介しようとすると、まずデータを探し、それをダウンロードし、自分で手を動かして図にするなど、大変な手間がかかります。FREDのように分かりやすく見せようとすると、さらに時間と労力が必要になります」
なんとかならないものか――。相馬先生はずっと思っていた。日本の経済データを集約したウェブサイトを構築しようという今回のプロジェクトは、そんな相馬先生のもどかしさ、怒りともいえる熱い思いから始まった。
余計な労力をかけず、「もっと使いやすく」を実現させる
「プログラミングの実地研修にもなるし、このようなデータがあることを知り、勉強するきっかけにもなる」そう考えた相馬先生は2024年前期、授業でプロジェクトに参加する学生を募集した。前述のFREDを参考にしながらプロトタイプの図(基本設計図)を作り、サイトのデザインを決めていき、本格的にウェブサイトを作り始めたのは8月になってからだ。
「せっかく作るなら何か新しい機能を一つ盛り込みたい」そこで、サイトで公開されているものと同じ図表を生成できるプログラミングコードを一緒に掲載することにした。そうすれば「学生や他の教員が同じようなグラフを作りたい、少し変えたいと思った時、一から作らなくて済みます」
国や民間企業等が提供している主要な統計データをグラフで提供する「統計ダッシュボード」の仕組みを使って用語解説も用意し、初学者の学びにつながりやすい工夫も講じた。同じ仕組みで、自動的に数値データが更新されるようにも設計している。

厳しい?指摘の連続でサイトはどんどん充実!
技術面は学生中心で進められ、各自が担当パートのたたき台を作り、みんなで意見を出し合いながら改善を重ねた。相馬先生が最もこだわったのが図の見せ方と操作性だ。何度もクリックしなくても目指すデータが表示され、おおざっぱにクリックしても誤操作にならないデザインにするなど、先生からはユーザー第一の視点で細かなチェックが入ったという。
サイトの制作は試行錯誤の連続で、現在も「いい感じ」に検索結果を表示できる方法を模索して、自然言語処理を使った仕組みづくりに奮闘している。
「プログラミングの知識がすごくあるわけではなかったし、機能を実装するのは大変でしたが、みんなから意見をもらうことで勉強になりました」
「自分で作ってみて動いていく様子を見て、プログラミングの面白さに気づきました」
「実際に使ってもらうことをイメージし、データが何を意味しているのかを考えながら作っていくことで、経済学の考え方を学ぶことができました」
このように、学生たちはそれぞれ制作の過程で多くのことを学んでいる。
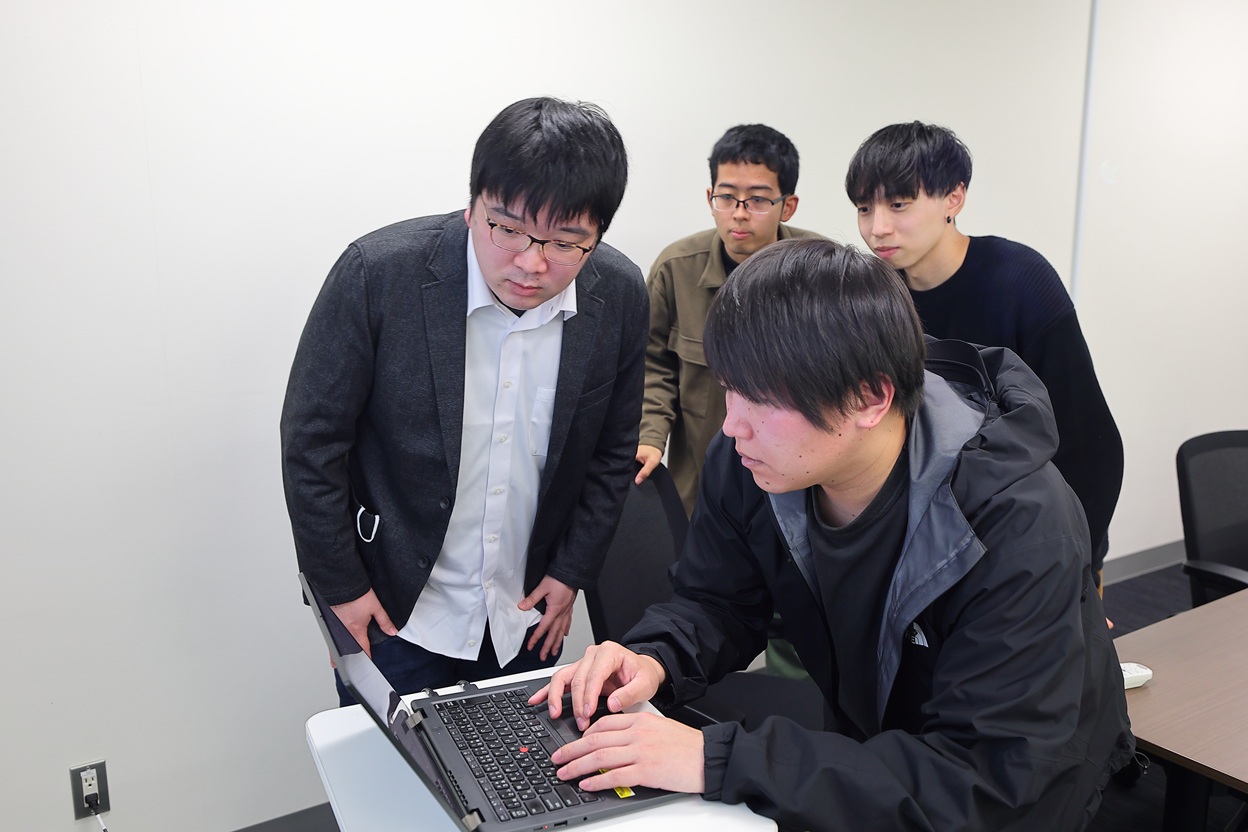
横浜国立大学経済学部を志望する皆さんへ
主要なマクロ経済のデータが手軽にワンクリックの検索で見ることができ、年次・月次・四半期などの単位も簡単に変えられ、使う人が利用しやすいデータ集をつくることを目標に始まったプロジェクトは最終段階を迎えている。2025年4月の公開後は1年生向けのマクロ経済学の授業でも活用される予定だ。
「世の中には日の目を浴びていないデータがたくさんあって、そこに光を当てることが大事です。このサイトはあくまでもたたき台で、とにかく、こういうものがあれば便利だという必要性に気づいてもらいたい」と相馬先生。
「大事なのは図にして見せることで、世の中の人がデータサイエンスに求めているのは、分かりやすく見せること、現状を見せることなんです。技術の進展とともに、それが圧倒的に手軽にできるようになってきたし、今後もプログラミングやデータサイエンスはずっと求められるスキルだと思います。今回、学生たちは勉強しながら、調べながらサイトを構築しています。ぜひ皆さんも作ってみてほしいし、何が必要かを考えるためにも、まずは経済学に興味を持ってもらいたいと思います」
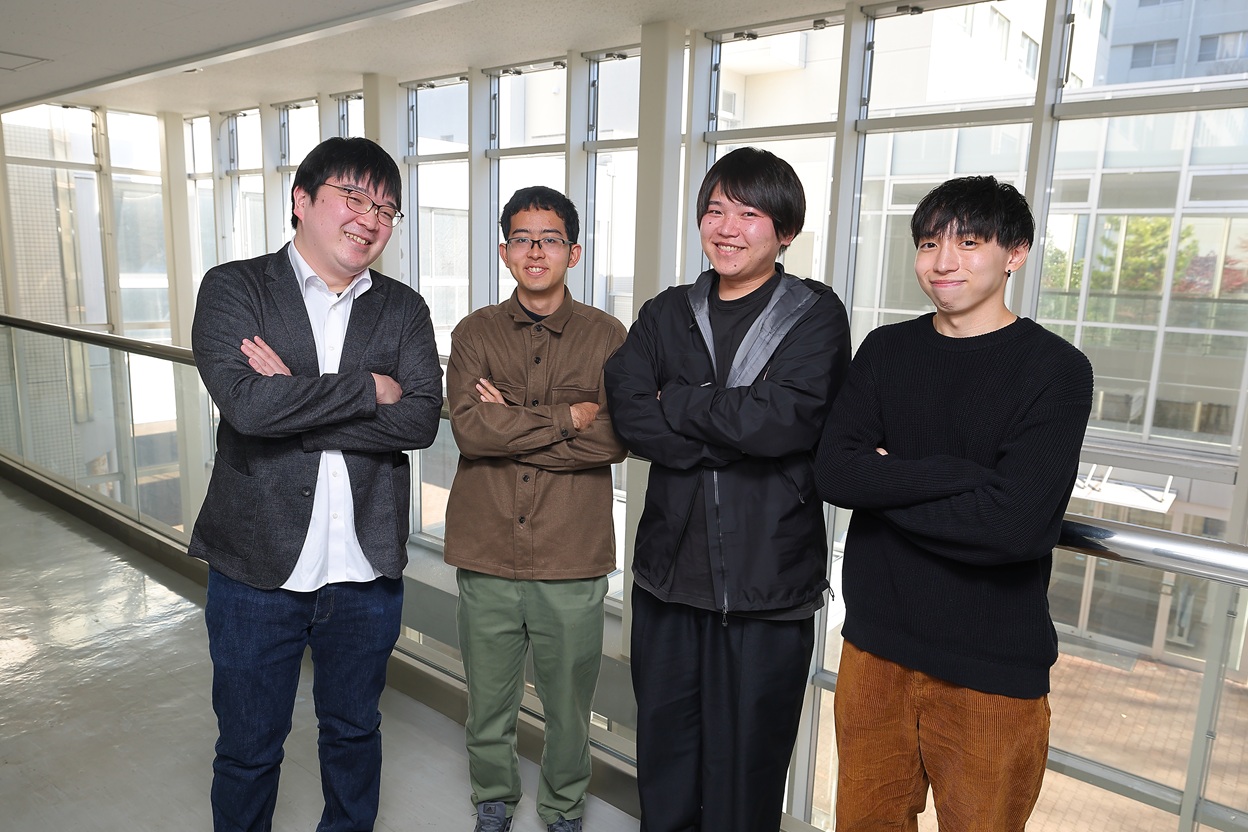
2024年度インタビュー