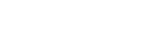国際教育
2016年度交換留学(派遣)生現地レポート
- エジンバラ大学
 YTさん
YTさん - オストラバ工科大学
 NNさん
NNさん - オージイン大学
 ASさん
ASさん - サンディエゴ州立大学
 TMさん
TMさん - カーディフ大学
 MOさん
MOさん - カーディフ大学
 SMさん
SMさん - イーストアングリア大学
 AHさん
AHさん - オスナブリュック大学
 YNさん
YNさん - セントイシュトヴァーン大学
 KTさん
KTさん - オタゴ大学
 YKさん
YKさん - マッコーリ大学
 STさん
STさん - シドニー工科大学
 SSさん
SSさん - シドニー工科大学
 KSさん
KSさん
YTさん
エジンバラ大学(University of Edinburgh)
平成28年8月~平成28年12月の月例報告より抜粋
9月分
大学に関する近況
9月8日にエジンバラに着き、10日に大学の寮へ入りました。最初の1週間はWelcome weekということで、学部ごとのオリエンテーション、サークルのイベント、パーティーなどに参加し、チューターの先生との面談、かかりつけ医師登録などをしました。またTEAM testと呼ばれる文法・語彙・リスニングの試験を受験し、基準点を満たしたため3・4年生向けの授業の履修が許可されました。授業はLabour Market Policy in Europe、The economics of Crime、Architectual Historyの3教科を履修することにしました。
個人の近況
寮は大学から徒歩で10分ほどのところにあり、3人のフラットメイトたちと生活しています。2人はロンドン出身で、1人は香港出身です。香港人のフラットメイトは4年前からイギリスに住んでいるためブリティッシュアクセントの英語を話し聞き取りやすく、英語の環境にはとても恵まれています。また全員とても良い性格で、大学のパーティーやサークルのイベントに何度か一緒に行きました。寮に入居しているのは1年生が中心で、イングランド出身の学生が多い印象を受けました。……私がダンスをやっていたことをFacebookを通して知った香港人の友人から、一緒に台湾サークルのイベントで踊ろうと誘われ、10月の中旬にK-POPを踊ることになりました。
その他
スコットランドは緯度が高いため、夏季は日照時間が長く夜の8時位まで外が明るいということに驚きました。また9月であっても気温が低く、冬物のコートを着ている人も多く見られました。気温の変化やイベントの多さなどの影響もありFresher's Fluと呼ばれる風邪の流行が起きルームメイトも全員風邪に感染しました。Welcome weekはイベントが多かったため外食や軽食で済ましていたのですが、風邪をひいたことをきっかけに食生活を見直し自炊を始めました。近くにアジア向けスーパーマーケットがあるため、日本の食材をほとんど手に入れることができています。シャワーのお湯が出ない日があったり、日用品や食材の容器、パッケージが異常に硬かったり、日本との違いに驚くことも多々ありましたが、次第に慣れてきました。
10月
大学に関する近況
授業で求められるレベルは高く、毎回の授業の予習に追われています。授業で学ぶことよりも、授業の前にどれだけ自分で学習を進めるかが大切である点が日本の大学と大きく異なると感じました。特に3週目~4週目は労働政策のディスカッションの司会、建築史のプレゼンテーション、建築史のエッセイの締め切りが重なっていたので、忙しい時間を過ごしました。エッセイは5つくらいのテーマの中から好きなテーマを1つ選ぶ形式で、さらにそのテーマが日本でのレポートよりも詳細に指定されているため驚きました。また、日本でのレポートよりも多くの参考文献を読んでまとめることが求められるので、エッセイを書く準備の段階から苦労しました。建築史の授業では、授業の一環としてモスクに訪れ、教科書で学んだことを実際に確認することができ、またモスクのスコットランドの建築様式の適応について知ることができとてもよい機会になりました。
個人の近況
10月前半は、勉強の合間を縫って友人たちとダンスの発表に向けて練習をしていました。学外の台湾文化イベントで踊ったのですが、見に来てくれた友人たちからの評判もよく嬉しかったです。月末にはSkye島というハイランドにある島を訪れました。火山活動の影響を受けた独特の景色に霧がかかっていてとても幻想的な雰囲気でした。スカイ島へ行く途中にはEilean Donan Castleをいう湖に浮かぶ城やネス湖などを通り、初めてエジンバラ以外のスコットランドの景色を見ました。留学生向けのツアーに参加したのですが、新しく中国人やオーストリア人の友人ができとても良かったです。
11月
大学に関する近況
全ての授業、課題が終わり、残すところは試験のみとなりました。・・・・・・11月の末には、Grammar for Academic writingというワークショップに参加しました。IELTSのwritingとも異なるacademic writingについてのポイントを学び、知らないことをたくさん吸収することのできた2時間でした。
その他
11月の半ばに貧血で目の前が真っ暗になり倒れ、その後体調が優れず1週間ほど家で過ごしていました。・・・・・周りの友人たちも、寒さや日照時間の短さのせいで体調不良や憂鬱な気分になっている人が多いので、運動なども取り入れて健康に過ごせるように心がけたいです。
12月
大学に関する近況
期末試験がありました。履修していた3教科すべてはレポートと期末試験の両方で成績評価をされる科目でした。5~6つのテーマの中から2つのテーマを選びそれについてエッセイを書くという試験形式で日本のものとかなり異なっていたため、とても困惑しました。教科書や授業内容を暗記しただけでは対応できず、関連分野の論文を読んで論点を整理し分析し、その内容について書くということが必要でした。・・・・・エジンバラ大学ではレポートについてのフィードバックを詳細にいただけるので、4年間通っていたら論文執筆の能力が上がっていただろうなと感じました。
個人の近況
クラスメイトに誘われクリスマスキャロルに行きました。歌詞がスクリーンに投影され、教会の中にもテクノロジーが組み込まれていることに驚きました。試験後には日本人、台湾人、マカオ人の友人とドイツ、チェコ、オーストリアへ旅行しました。ドイツはケルンとニュルンベルクを訪れたのですが、特にケルンの人々は英語が大変上手でした。ホテルや観光地の方など直接英語が必要な職業の方のみならず、駅員やスーパーの店員まで英語を流暢に話すことができ感銘を受けました。
NNさん
オストラバ工科大学(VŠB Technical University of Ostrava)
平成28年8月~平成28年12月の月例報告より抜粋
9月
大学に関する近況
僕が大学寮に到着したのは9/5でしたが、入寮するために、事務室の前に学生の長い列がありました。
今思えばおかしなことなのですが、到着した当初、周りの留学生が学生に見えなかったので、話しかけることもなく本を読みながら時間を潰していました。しかしながら、ユーロ圏から来た(と思われる)学生の体格を見ているとやはりアジア人と違うなあと感じました。身長、肩幅、胸板どれをとってもデカい。
話しを戻しますと僕の到着した9/5から授業開始までの1週間の間に多くの学生が学生寮に入居していたと思います。僕の場合5,6時間並んでいたような気がしますので、並びたくない方は早めに到着されることをお勧めします。そしてこの1週間の間は、学生寮前のクラブで到着した学生がビールを飲み交わし交流していました。(雰囲気で言えば、大学の学科交流会みたいなものですね。) 国際交流にあまり興味がなく、海外も一度しか経験したことのない僕にとってはなかなか新鮮でした。トルコ人やドイツ人、スペイン人、ポーランド人などなど様々な人がいました。9/6からオリエンテーションが始まり、授業に関する説明や、トランスポーテーションカード(通学定期券みたいなもの)の作り方、またチェコ、オストラバに関する説明を一通り受けました。そして、ウェルカムパーティーやオストラバ市街での飲み歩き、動物園への遠足などが催されました。これらの行事ですが、ESNという留学生支援の学生団体主催で物事が進んでいきます。留学前にメールをチェックし忘れていたのですが、WEB上で登録して、学生ひとりひとりにESNの学生がついてサポートしてもらえます。またFacebookでチェックしておいた方がいいです。
次に授業に関してですが、大学で学んでいた計量経済学、統計学とチェコ語とプログラミングとWEB デザインの授業を履修しています。履修の最低水準(20Credits)を満たしていなかったようで、国際課の方から連絡がきました。
授業内容はどれも初学者向けになっています。特にプログラミングとWEBデザインの授業は小学生のように先生のモニターを見ながらそれを真似ていくような形の授業形式です。しかしながら、計量経済学は授業名こそIntroduction to Econometricsなのですが、学んでいた人じゃないとついていくのは厳しいんじゃないかなという内容になっています。テンポよく定常、季節性変動、トレンド、多重共線性などの用語が用いられながら、授業は進んでいきます。内容がわからなくとも統計ソフトのボタン一つでなんとかなるのが悲しいところですが。僕は大学で計量経済学を学んでいたので問題はありませんが、こういうこともあるので今後留学される方は気をつけてください。この授業では最終的に時系列分析のレポートを書きあげ、プレゼンテーションを行います。なにか新しい分析ができたらいいなと思います。
個人の近況 留学に来る前は就職活動があったり、留学費用のためにアルバイトを詰め込んでいたりして正直英語の勉強もなにもしていませんでした。英語もままならないまま、こちらに来てしまいましたが、運のいいことに韓国、ポーランド、トルコの友達が出来ました。最初は少し英語を話すことに恥じらいを感じて全く話せませんでしたが、今はなんとかやっているという状況です。授業の空き時間などには韓国人たちとテニスを楽しんでいます。
また、ギターが趣味だったので、クラシックギターを買い、ギター教室に通っています。
講師の先生(Petr)はチェコ人で、英語でレッスンを受けています。クラシックから現代音楽まで演奏されている方で毎週楽しくレッスンを受けています。大学寮にはピアノ室があり、そこで暇があれば練習しています。大学の前にジャズクラブがあるのですが、有名なアーティストが頻繁に来られていて何度か行きました。オストラバはあまり都会だとは思えませんが、音楽が身近に味わえる良い街だと思います。ヨーロッパという視点から見てみると、現代音楽のコンサートがドイツ、ウィーンで行われていてヨーロッパの音楽文化が生きているのだなと感じました。
その他
長期ビザに間に合わず、長期滞在許可を申請していましたが、 長期滞在許可証の受け取りに行きそびれたので今週、外国人警察の方に手続きに行ってきます。
10月
大学に関する近況
授業に関しては9月と相変わらずという印象です。
プログラミング、ウェブデザインの授業では先月同様、先生のモニターを自分のパソコンに写してプログラミングを覚えていくという単調な作業です。計量経済学に関しても、教授が生徒を置いてけぼりにしたまま、授業が終わり、その次の演習の講義で分析の手順を真似ていくという作業です。いくら単調な授業とは言え、どの授業でも来月で授業のほとんどが終わってしまうので最終的な課題への取り組みが進んでおり、少しずつ緊張感が高まっているような気もします。
個人の近況
9月末から急に気温が落ち込み、平均気温が10度を割り込むほど寒くなっています。
寒いだろうと思って前もってアウターを購入していたので、急な気温の変化に対応することが出来ました。しかしながら、10月中旬に風邪をひいてしまい一週間ほど休んでいました。
大事には至らなかっただけ幸いと思います。また、9月は毎朝のようにランニングに出かけていましたが、寒くなってからは全く走らなくなりました。部屋に籠りがちになってしまいました。日本から少なからぬ量の本を持ってきていたので最近ではもっぱら部屋で本を読んで過ごすことが多くなりました。
その他
無事に長期滞在許可を受け取ることが出来ました。
ASさん
オージイン大学(Ozyegin University)
平成28年8月~平成29年1月の月例報告より抜粋
9月
大学に関する近況
9月17日に大学に到着した二日後の月曜日には、早くも授業がスタートした。この学期最初の1週間はオリエンテーション期間ともなっていたが、授業も通常通りしっかりと行われクラスによっては早速宿題も課された。この翌週の水曜日には履修登録期間が終了してしまうため、まだ大学に関して右も左もわからないまま非常に慌ただしく授業に向かった。渡航前に履修希望科目を提出していたが詳しいスケジュール等は学期が始まってみなければわからなかったため、申請したもののうちいくつかは時間割がかぶったりパイロット養成向けの授業だったりしてとることができなかった。オージイン大学は法学部を除き全ての学生が英語で授業を受けており、いわゆる留学生向けの授業は存在しない。したがって授業では自分以外は基本的に全員現地のトルコ人学生であり、すぐに周りに溶け込むのはなかなか難しいと現在感じている。授業は基本的に3年生以上向けのものをとっており、各授業で毎回課題が出るので、一つ一つがハードに感じる。・・・・・・授業以外では、到着翌日の日曜日に全学向けのオープニングセレモニーがあり、その後簡単なキャンパス見学が行われた。授業開始日である19日の午後には1年未満の短期留学生向けのオリエンテーションが行われ、諸々の手続きに関する説明を受けた。現在の国内情勢もあってか、短期留学生の数は非常に少なく、10人に満たない。以上のような状況から、前回のハンガリー留学時に比して留学生のコミュニティが小さく、また本大学にはESNという多くの欧州の大学にあるような短期留学生の支援・交流を行う組織がないため、人脈を広げるのが非常に難しい。
個人に関する近況
現時点までで特に課外活動・クラブ活動等には参加していない。ただ、オージイン大学は近年できた新しい大学でスポーツセンターなど施設が非常に充実しているので積極的に利用していきたいと考えている。前述のように本大学にはESNがないため、基本的に留学生向けのイベントは無いと思われるので、折を見て全学向けの通知などから情報収集して何らかの活動・イベントに参加していきたいと思う。
その他
留学地がトルコということでテロやクーデターという厳しい情勢から渡航前は少なからず不安があったが、これまでイスタンブールの街の様子を見た限りでは、特に変わったところはなく渡航前に想定していたよりも落ち着いているというのが現在の印象である。・・・・・次に大学のキャンパスに関して、イスタンブールの中心部からはかなり離れており、交通状況にもよるが大学のシャトルバスやその他公共交通機関を乗り継いで中心部まで1〜2時間ほどかかるので、その点は非常に苦労する。最後に寮に関して、キャンパス内も含めて食堂やカフェが充実している反面、自室にキッチンが無く、また寮の中にある共同キッチンは非常に小さくて数も少ないため、未だ自炊ができていないのが現在の悩みである。
10月
大学に関する近況
トルコに到着してから約1ヶ月半が経過した。履修登録や教室変更も終わり授業に参加する学生も定まった。授業の内容そのものは到着直後からそうであったように次々と先へ進んでいった。私がとっている授業の学生数は大体10人から30人ほどの振れ幅である。先月にも述べた通り、各授業でほぼ毎回課題があり、特徴としてはグループで取り組むものが非常に多い。また既に一つの授業で中間試験を終え、これから他の授業において中間試験やケースレポート提出が予定されている。そのため、この頃はほぼ毎日のようにレポート課題及び試験の準備に追われており忙しく感じている。
個人の近況
最近はスポーツセンターやレストラン等、大学にある各施設の利用にも慣れてきた。大学からの通知で様々なスポーツの大会が大学で開催されることが分かった。そのうち友人のチームに誘われサッカーの大会に参加することになり、近々初戦を迎えるので頑張ろうと思っている。
その他
在イスタンブール日本領事館からしばしば治安情報をメールで受け取るが、今後もテロには十分に注意していかなければならないようである。このような情勢に加え、授業が予想以上に忙しく友人とスケジュールが合わないということもあり、トルコに来てから一度も旅行にでかけていない。またイスタンブール名物の渋滞で中心部まで行くのに1時間以上かかるので買い物等に出かけることも少なく出不精になっており、生活の大部分をキャンパス内で過ごしている。
11月
大学に関する近況
11月となり、学期は中盤から後半にさしかかり多くの授業で中間テストの実施及び様々な課題の提出が相次いだ。中間テストについては、概ね良い点を取ることができた。横国での一般的な授業と異なり、テストで望ましい点数を取ることができたとしても試験以外の多くの課題による成績面での比重が大きいので、学期中は常に気が抜けない。この月は成績に相当程度関わってくる課題の提出が多くあったが、それらのほとんど全てがグループ課題であった。グループのメンバーと連絡を取り合い授業時間外に集まったりスカイプを介して作業を行ったりしたわけだが、皆それぞれ試験や他の多くの課題で忙しいので課題が完成するのは締め切りぎりぎりになってしまうことが常であった。横国ではゼミ以外でグループ課題はほとんどないので、この点も大きな違いである。
個人の近況
今月初めに大学のサッカー大会で、自分が所属するチームのグループリーグ初戦が行われた。自チームは連携がおろそかで試合中はイライラすることが多く、なんとか初戦は制したものの続く第2戦では敗れてしまった。
その他
早くも留学が終盤に差し掛かっているので、引き続き頑張っていければと思う。前回のハンガリーでの経験があるので、トルコの冬はまったく寒く感じないが、油断せず体調に気をつけて過ごしていきたい。最近イスタンブールでは雨の日が多いが、トルコ人は短い距離なら濡れることを気にしないのか、(かなり強い雨でも)キャンパス内で傘をささない人が多いのは日本と違って面白いと感じた。
12月
1月
大学に関する近況
大学に関する近況 1月は13日まで期末試験及び最終課題の提出期間となっていた。履修している授業のうち半分の試験・課題は12月末までに終えていたので、1月は残り半数に取り組んだ。・・・。ちなみに、1月第2週はじめ頃にイスタンブールで再び大雪があった影響で郊外に位置する大学とその他停留所を結ぶシャトルバスが2日間ほど運行休止となってしまい、試験日程が直前で変更されたりして試験期間後半は少し慌ただしかった。自分の試験はどうにか13日に終わったのだが、知人の学生の中には試験がそれ以降にずれ込み日曜日にキャンパスに来て試験を受けている者もいた。試験期間終了をもって秋学期も終了となり、30日の second semester 開始日まで休暇期間となった。
個人の近況
試験終了後の1月21日〜26日にハンガリー留学時代の友人とロシア旅行を計画していたので、試験のほかにロシア観光ビザ申請のための必要書類の準備で1月は忙しかった。ロシア旅行代理店発行の証明書のようなものの原本が年末から待ち続けて16日にようやく届き、その日に急いでイスタンブールでビザの申請をしたので旅行までにビザが手に入るか心配であったがなんとか出発前日に取得することができた。余談だが、ビザを受け取りに再びイスタンブールのヨーロッパ側の地区を訪れた際、通りに黒いプラカードを持った多くの人々が集まっていて警察も大勢警備につき交通規制がなされ、ビザセンターまでの道のりで何度か身体・荷物チェックをされたので一体何のデモかと思ったのだが、後に調べてみるとちょうど10年前に暗殺されたフラント・ディンクという著名なジャーナリストの追悼イベントが行われていたようであった。
TMさん
サンディエゴ州立大学(San Diego State University)
平成28年8月~平成29年6月の月例報告より抜粋
8月分
大学に関する近況
8月25日に留学生のオリエンテーションがありそこで正式に留学がスタートした。オリエンテーションでは大学に関する様々な説明があり,これを通してたくさんの留学生と知り合う機会を持つことができた。そこから28日まではアメリカの学生が入寮する時期であり,私のハウスメイト4人もこの時期にそろった。また市内観光や動物園ツアーなどでサンディエゴの名所を回ることもできた。29日に授業がスタートして本格的に大学が始まった。今期は専門の経済に関する授業としてPrinciples of EconomicsとIntermediate Macroeconomics,英語のライティングスキル向上のための授業としてDevelopment Writing for International or Bilingual Students,現地の学生との交流を目的としてAdvanced SoccerとElementary Japanese 1の5クラス計12単位を履修する予定である。1セメスター目ということもあり専門の授業は日本ですでに履修したもので,単位数に関してもこちらで最低必要とされる12単位にとどめた。今学期はサンディエゴ州立大学の日本語コーディネーターの方のアドバイスを参考に,こちらでの生活に慣れ,授業の雰囲気やペースをつかむこと,また友人関係を構築することを重視していきたいと思う。
個人の近況
学生寮での生活には徐々に慣れてきた。on campusの寮ではあるが大学が広いため大学の中心に行くのだけで15分ほどかかってしまう。大学外の買い物に関しては,トロリーとバスがあるものの行けるところが限られているため車のない学生にとっては不便に感じる。気候は基本的に毎日晴れで雨が降ることはない。日差しが強く日中は暑く感じるが,日本の夏のような蒸し暑さはなく過ごしやすいと思う。朝と日没後は半袖では寒く感じるくらい気温が下がる。
その他 出発日の8月22日は台風が日本列島に直撃し空港まで行くのに苦労したりフライトが遅れたりと少し大変だったが無事その日に大学の寮に到着することができた。8月24日に留学生のチェックインがあったがその際に空港で押されたビザのスタンプに間違いがあることが分かりサンディエゴ市街にあるBoarder Protectionまで行くことになってしまった。無事訂正が終わり大きな問題はなかった。
9月
大学に関する近況
授業がスタートしてちょうど1か月ほどたった。8月の報告書ではPrinciples of Economics,Intermediate Macroeconomics,Development Writing for International or Bilingual Students,Advanced Soccer,Elementary Japanese 1の5クラス計12単位を履修すると報告したが,せっかくなので経済の授業をもっととりたいと思いDevelopment Writing for International or Bilingual Studentsの代わりにInternational Economic Problems の授業を履修することにした。授業は英語が聞き取りにくいことはあるが,日本で学習した知識があるため予習復習をしっかりやることでついていくことができているように感じる。毎週課されるオンラインの宿題も順調に解けている。先日こちらに来て初めてのテストがあった。自分の部屋でPCに向かって行うオンラインテストで少し違和感があった。
個人の近況
授業が始まって生活のリズムが定まってきたことで生活が落ち着いてきたように感じる。平日は基本的に授業の予習や復習,宿題を行い,息抜きにルームメイトと卓球をするといった生活を送っている。休日は平日に終わらなかった勉強を片付けるとともに,大学内のジムに行ったり,友人とイベントに参加したり,近くの観光地に行ったりしている。・・・・・・・食事に関しては,大学内のファストフードを利用できるミールプランを使用しているが,健康面や金銭面を考えて休日などは自炊を始めることにした。・・・・・・また,少し離れた場所ではあるが,サンディエゴには日系スーパーもあるため日本の調味料や日用品も必要であれば手に入れることができる。
10月
大学に関する近況
10月が終了し秋学期も後半戦に突入したところである。どの授業もmid term が無事終了した。現時点では全ての授業でAをとれるほどの成績であるためこの調子で勉強を続けていきたい。授業の中身についてだが,基本的にすべて日本で学んだ内容であるため全く新しいことという感覚はないが,それでも教え方や扱う内容に少しの違いを感じる。例えばIntermediate Macroeconomics の授業では数式をなるべく利用せずに言葉を用いて説明するということが要求されている。教授は概念を理解してそれを言葉で説明できるようにすることが数式を解くよりも将来役に立つと繰り返しおっしゃっている。International Economic Problems の授業では週2回ある授業のうち1回は教科書に基づいたレクチャーを行い,もう1回は内容に関係するドキュメンタリーを観るというやり方をとっている。教科書で学んだ理論を実際の経済に当てはめて考えることが狙いである。レクチャーの聞き取りはまだ完ぺきとは言えないので聞き取れるように集中して授業を受けていきたい。
個人の近況
10月に入って日が沈むのが早くなり秋らしくなってきた。それでも太陽の出ている日中は半袖で十分なほどの暖かさであり改めて気候の良さを実感している。しかしエアコンをつけっぱなしという部屋の環境のせいもあり乾燥が少し気になる。・・・・・・今月末はHalloweenもあり土日等はみんなで盛り上がる機会が多かった。また来月のThanksgiving や12月から1月にかけての約1か月にわたるWinter Break の計画も立て始めている。11月中にはきちんと計画を立てることになるだろう。車がないため買い物には相変わらず苦労しているが,車を持っている学生にお願いしたり,Uber やバス,トラムを利用したりして何とか生活している。
11月
大学に関する近況
秋学期の授業も終盤に差し掛かってきた。11月の前半にMid Termが一通り終わり,Thanksgivingの休みを挟んで現在はFinalに向けて勉強しているといった状況である。Thanksgivingの休みはアメリカの学生にとっては重要なものであるため,休みの前後の授業はキャンセルになったり出席する学生が少なかったりというような状況であった。休み明けも一部の学生はまだ帰ってきていないようで,教室に空席が目立つ印象をうける。成績に関してはここまでしっかりととれているためFinalでもよい点数が取れるようしっかりと勉強をしていきたい。しかし,私が今学期とった授業はどれもテストで成績が決まるものであり,レポート課題やグループワークは特に課されていないためそれほど大変ではないように感じる。11月の半ばには来学期のクラススケジュールも発表されたため少しずつ来学期のタイムテーブルの検討を始めている。
個人の近況
Thanksgiving Breakはとても充実したものとなった。アメリカの学生はほぼ全員が実家に帰るため寮がさみしくなると聞いていたが,地元の友達の家に行かせてもらえたため楽しむことができた。5日間の休みの間にはKnott's Berry Farmという人気のアミューズメントパークや映画,アイススケート等に行った。Thanksgiving当日は友達の両親が伝統的なThanksgivingの食事をふるまってくださり,他の国からの留学生も交えて各国の伝統や文化について話をするなどとても有意義な時間を過ごせた。11月半ばくらいから気温が下がり始め冬の気配を感じている。とくに日没後は非常に寒く感じるようになった。とはいえ日中は半袖で過ごせるほどであり,日本に比べると快適な気候であることに変わりはない。体調管理だけはしっかりと行っていきたいと思う。
12月
大学に関する近況
12/19で全てのFinalが終わりWinter Breakに入った。30日までには成績もすべて出そろい,正式にFall Semesterが終了した。Finalも大きく失敗することなくどの科目も9割前後の点数を取ることができた。・・・・・大学の雰囲気はテストが終わるとすぐにクリスマスであったこともあり,テスト後は一気に学生がいなくなった印象を受ける。Winter Breakの間はキャンパスや寮にほとんど学生のいない状況である。来学期は1/18日が最初の授業であるが,1/10から履修登録が開始されるので来学期のクラスもしっかりと考えていきたい。
個人の近況
12/20から12/27まではルームメイトの実家に泊まらせてもらい,観光を中心に様々な経験をさせてもらった。・・・・・・また,多くの交換留学生は1セメスターで帰ってしまったため,寮は全体的にひっそりしている。
1月
大学に関する近況
1/18から春学期が始まった。秋学期はある程度の知識のある比較的簡単な授業をとっていたので,今期はあまり学んだことがなく,こちらでしか開講されていないような授業を中心に履修している。経済の授業はBusiness Cycles, Economic History of the U.S., Economics of Work, Marriage, and Family の3つをとった。どの授業も日本ではあまり学んだことがないため少しハードではあるが興味深い。他にはFinancial Literacy という授業をとった。これはSDSUではGeneral Education のひとつとなっていて,様々なメジャーの学生が履修している。Personal Finance がメインテーマで将来の役に立ちそうな内容である。またアクティビティーの授業はAdvanced Soccer とSurfing を履修した。4つの授業全てでリーディングが必要であり,授業が始まってからはリーディングに追われている。また,オンラインディスカッションやプロジェクトもあり,秋学期に比べて勉強が忙しくなったがしっかりと続けていきたい。
個人の近況
・・・・・天気に関しては,夏や秋に比べて雨の日が多かった。1/20には近くの川が氾濫するほどの大雨が降った。しかし,それ以降は晴れの日が続いており,気温も20度を超えるようになってきている。
2月
大学に関する近況
春学期の授業も中盤に入ってきたのでそれぞれの授業の内容について説明していく。先月の報告書でも書いた通り,今学期は Business Cycles, Economic History of the U.S., Economics of Work, Marriage, and Family, Financial Literacy, Surfing, Advanced Soccerの計6クラスを履修している。Business Cycle は様々な学派のマクロ経済学を理解すること,主要な経済データの見方を学ぶことがメインテーマである。SDSUの経済の授業の中では中級マクロの次の段階というような扱いである。Economic History of the U.S. は授業の名前の通りアメリカ経済史がテーマであり,長期間にわたる経済データをもとにアメリカの成長をたどっている。この授業はドキュメンタリーを観たり,クラスディスカッションやオンラインディスカッションを行うやり方をとっている。Economics of Work, Marriage, and Family は担当の教授が考えたHousehold Economics の枠組みを学ぶ授業でとても特徴的である。経済学部の授業の中ではあまり扱われないテーマであるため難しく感じる時もあるが,興味深い授業である。授業の進め方はレクチャーベースで,最後15分ほどは学生からの質問や意見を中心にクラス全体で簡単なディスカッションを行っている。Financial Literacy ではパーソナルファイナンスの基本的な考え方を学んでいる。税金制度や預金,クレジットカードの利用方法など日本とアメリカの制度や文化の違いを感じることが多く,とてもおもしろい授業である。Surfing とAdvanced Soccer はとても楽しくできている。サンディエゴはサーフィンをするのに最高の環境ということもあり,とてもいい経験ができていると感じる。サッカーは前の学期に比べて履修者が多くより充実した授業になっている。
個人の近況
今学期はアカデミックな授業を4つ履修していることもあり,週末はテキストのリーディングに追われている。しかし,夜は同じ寮の中に住む友達と卓球やビリヤードをしたり映画を観たりしてとても楽しく過ごしている。みんなに日本語を教えたり,逆に他の国の留学生からその国の言葉を教わったりと貴重な経験をしていると感じる。また,仲良くしている友達が同じ授業をとっているため,テスト前などは一緒にテスト勉強をしており,これもとてもいい経験ができていると思う。気候に関しては,2月半ばくらいから昼間の気温が20度を超えるようになってきて日差しも強くなってきたように感じる。
帰国日が決まったのでお知らせします。5月12日発のフライトで帰り,日本到着は13日の予定です。
3月
大学に関する近況
3月は授業も折り返して後半戦に入るころだった。そのためどのクラスも中間試験があり、1月、2月に比べて少し勉強が大変な月だったように感じる。しかし、きちんと勉強時間をとれたおかげで、どのテストも自分の中で目標としている90%をクリアすることができた。4月はテストが1つしかなく残りのテストはファイナルだけなのでファイナルでも目標とする点数が取れるようにしっかりと勉強していきたい。4月はテストの代わりにプレゼンテーションや課題の提出があるため、現在はその勉強に追われている。
個人の近況
上の項目で書いた通り、3月はテストが多く勉強に時間を割かなければいけなかったが、その中でも休日は友達と色々なことを経験できたと思う。特に印象に残っているのが、ラ・ホーヤという場所で行ったシーカヤックである。名前の通りカヤックで海を回るツアーで、ラ・ホーヤの説明を聞いたり野生のアザラシを観たりすることができた。
4月
大学に関する近況
4月はどの授業も終わりに向けてまとめの内容が多かった。先月の報告書でも書いた通り、今月はテストは1つしかなく、代わりにプレゼンテーションや課題の提出があった。どれも無事に終えることができ、きちんと点数もとれていたので一安心といったところである。5月に入ると1週目が最後の授業、2週目がFinal Exam になるので4月の終わりからは少しずつFinalの準備を始めている。これからはFinalの準備と同時に帰国準備や寮のチェックアウトの準備などがあり色々と忙しくなることが予想されるが、最後まで集中して授業やテストに取り組みたいと思う。
5月
大学に関する近況
5月は最初の1週間が授業でその後は期末テストだった。期末テストが終わったらすぐに帰国することになっていたので留学生活も残り2週間であった。テストに関しては履修していた4科目すべてで85%以上取ることが出来たため、春学期の授業に関してはオールAを達成することができた。
個人の近況
5月に入ってからは期末テストの準備、チェックアウトや帰国の準備、友達たちとの最後の思い出作りととてもあわただしい日々が続いた。特に部屋の掃除やチェックアウトの準備は大変であった。部屋の掃除は共用スペースをルームメイトと分担して掃除する必要があったり、チェックアウトの手続きは自分のテストスケジュールを考慮しながらチェックアウトの時間を事前に申告しなければならなかったりとしっかりと確認して行う必要のあることが多かった。
MOさん
カーディフ大学(Cardiff University)
平成28年8月~平成29年6月の月例報告より抜粋
9月
大学に関する近況
9/19から新学期が始まった。カーディフ大学は、町の中心部に隣接した行政地区内に立地しており、裁判所やウェールズ自治政府、市役所などと隣接している。文字通り世界中から学生が集まっているが、近年は中国からの留学生が多いようである。始業式において、学部長が経済学部のイギリス/世界における指導的な立ち位置、抱えている課題、それらを踏まえた施政方針を熱弁しているのが、非常に印象的であった。日本の大学にもこうした母校への矜持があってもいいのではと思った。
開発経済や国際経済史にかかわる授業を履修している。授業は講義とチュートリアルと呼ばれる少人数セミナーに分かれており、50分一コマでの講義が週2回、チュートリアルが週1回のペースで開かれる。どの授業も、経済学にとらわれず政治や社会情勢を含め学際的に扱っており、非常に面白い。
個人の近況
寮での生活がスタートした。寮は経済学部講義棟から徒歩で30秒ほどの距離であるうえ、中心部までも歩いて10分ほどでアクセスできる好立地である。寮は1フラットが各入居者分の居室と共同のキッチンで構成されるフラットという基本単位があり、自分含め8人が同じフラットで生活している。7か国の学生が一つ屋根の下で生活している。英語のアクセントも多種多様で、リスニングには非常に苦労している。
カーディフの物価は英国のほかの主要都市に比べ非常に安く、ロンドンの半分ほどの水準である。横浜と比較してフルーツや野菜などは非常に安価であるが、大学周辺のランドリーは非常に高く一回500円ほどかかる。ただ総じて、物価は横浜と同等もしくは同等以下であるように感じる。
10月
大学に関する近況
大学が始まって一か月半が経過した。授業の内容も導入から、専門的なものが増え大量の予習課題が課されるようになった。授業は、required readingを読んでおかないと、よく理解できないので予習は必須である。予習、授業、復習のサイクルを作らないと授業の内容をしっかり消化することは難しいように感じる。
"International Economic History"の授業では、現在Great Divergenceを勉強している。産業革命後の200年で各国間の所得格差がそれまでになく乖離し始めた事実に対し、そもそもなぜ産業革命はイギリスで起こったのか、なぜ中国では起こらなかったのか、またその後も持ち得る国と持たざる国の格差が収斂することなく加速度的に拡大していったのか、といった率直な問いを立て、Divergence(乖離)の所以を紐解いていく。
"Economics of Development"という授業では、経済成長や国民福祉の向上を図る指標として、GDPの有効性を批判的に考察している。GDPは家事労働などの市場を介さない経済活動を組み込むことができない点や、所得格差を考慮しないといった特性を踏まえて、なぜこれほどまでに広く利用されているのか、もしくはGDPを補完し得る指標としてどういったものが存在するのか、といった事柄を扱っている。
個人の近況
サマータイム期間が10月30日に終了した。30日はいつもより1時間長かったのでその分長く寝られてラッキーだった。10月の半ばころからかなり寒くなってきて、最近では朝晩は5度を下回る日もある。東京の12月中旬位の感覚。中旬にロンドンで開かれた開発学のセミナーに参加してきた。JICAの英国事務所の駐在員の方を講師に招き、日本の開発協力などについての講演だった。セミナーのついでに、ウェストミンスターや大英博物館なども観光した。
11月
大学に関する近況
授業が始まり二か月が経過し、内容も徐々に専門的になってきている。国際経済史の授業では、19世紀におけるアメリカの経済発展において鉄道の果たした役割についてSocial Saving理論を応用して考察している。開発経済の授業では、国内の統治制度が経済成長に与える影響などについて学んでいる。イギリス政治の授業では、最近Brexitについて扱った。地域や年代によって投票行動に乖離が見られたことや、キャメロン政権がレファレンダムを実施するに至った政局的背景を学び、大変面白かった。
12月
大学に関する近況
大学は10日からクリスマス休暇に入った。授業期間はとても賑わっていたキャンパスも今は閑散としている。ヨーロッパから来ている学生のほとんどが規制している模様だ。ただ、年明けすぐにテスト期間に入りその期間にレポート課題などの提出期限が設定されていることも多いため、24時間開館している図書館では多くの人が勉強している。自分は、3つのエッセイをなんとか完了させ、テストはないため、しばしゆっくりできる見通し。
個人の近況
12月の初めに、トビタテイギリス留学生の同窓会がロンドンであり参加してきた。火山学、スポーツビジネス、ファッションと多様な専門分野を持つ人々が集まり、とても有意義で刺激を受けることのできた会であった。また、ロンドンに赴いたついでに、帝国戦争博物館も訪れた。広島の原爆資料館を訪れて以来、戦争系の博物館に非常に興味を持つようになったため、渡英前から行きたいと思っていた。入館が無料であるにもかかわらず、展示が非常に充実していてとても面白かった。やはり書籍や授業でいくら戦争史や核抑止理論を勉強しても、なかなかしっくりこないことが多いのだが、こうした博物館に行くと戦争の悲惨さがリアルに体に入ってくる。また訪れたい。
1月
大学に関する近況
12月9日以降、クリスマス休暇とテスト期間で中断していた授業期間が1/23に再開しました。2か月に及ぶ授業期間が始まります。やはり英語でのレクチャー、ディスカッションは大変ですが、あと2か月授業を受け、イースター休暇を経て期末テストを終えたら帰国だと考えると、あっという間に終わってしまうなという実感です。
個人の近況
トビタテで計画していたインターン/ボランティアで、オックスファムという英国のNGOでお世話になっています。オックスファムは英国中に700近くのチャリティショップを展開し、市民から受けた寄付を販売しその売り上げを活動資金としています。英国の開発NGOについて学ぶことを柱にして計画した留学計画だったので、日々新しいことを学ぶことができ良い経験ができています。
2月
大学に関する近況
春セメスターが開始して一か月が経ちました。今学期からアカデミックスキルのクラスの授業を取り始めました。エッセイなどのアカデミック文章の書き方を主に扱っています。ほかの大学も同様だと思いますが、カーディフ大学では剽窃に対して非常に厳格なスタンスを取っており、参照や引用の方法などもきちんと習得する必要があります。英語エッセイは日本語のレポートとは構成が大きく異なることもあり、英語ライティングの授業は非常に意義深いです。
個人の近況
休日を利用して、バースという隣町に日帰りで行ってきました。Bathという名の通り、ローマバスの遺跡が残存しており、こじんまりとして落ち着いた古い町並みがとても印象てきな素敵な町でした。
3月
大学に関する近況
春セメスターは4月7日までですが、多くのモジュールは最終週の授業を行わないので、3月31日をもって春学期も実質終了です。秋学期に引き続き、開発経済や国際経済の授業を履修しました。授業を受け始めた去年の9月頃に比べ、教授の英語もだいぶ聞きとれると実感する瞬間がおおくなりました。
個人の近況
大学の授業とオックスファムでの実践活動に加えて、英語の勉強に少し力を入れた一か月でした。
4月
大学に関する近況
イースター休暇のため授業などはありませんでしたが、5月にテスト期間を控えているので、多くの学生が遅くまで図書館などで勉強していました。四月初めに1つ、5月初めに3つのエッセイの提出期限があり、また3つのテストも予定されているため、基本的にテスト対策などに多くの時間を割きました。英語での答案の作成は日本語とは比べ物にならないほど大変なので、しっかり対策をしたいと思います。
個人の近況
カーディフはかなり日が長くなってきました。3月26日のサマータイム開始によってたった一日で1時間も日没が遅くなったわけですが、それにしても21時ころでも街灯なしで町を歩くことができます。また天候も非常に良好で、渡英した当時のさわやかな秋を思い出します。ただ、気温はあまり上がらず、日中でも15度前後、朝晩になると10度を下回るので、長袖が欠かせません。
5月
大学に関する近況
4月30日で三週間のイースター休暇が終わり、5月はまるまる一か月テスト期間でした。5月初めに3つのエッセイを抱えていたので、4月中旬からずっとそれらに取り組みながら、エッセイののちは息をつく間もなくテスト勉強に移行しました。テストは15日、17日、6月1日と3つあり、英語での答案作成に苦労しながらもなんとか3つやり遂げました。図書館はどこも満員で、こちらの学生は本当によく勉強するなとひしひし感じながら自分も負けじと試験準備に取り組みました。
個人の近況
5月も相変わらず日が伸び続け、今では22時頃でもまだ明るいです。エジンバラなどの北部では11時ころまでまだうす暗いと聞きました。ただ、高緯度にあるため、気温は相変わらず20度を下回ることも多く半袖ではすこし肌寒いです。テストがあってかなりstressfulな一か月でしたが、6/3に欧州チャンピオンズリーグの決勝が大学から徒歩5分ほどのウェールズ国立競技場であり、30万人のカーディフに17万人が押し寄せました!大会期間中は、往年のレジェンドプレーヤーたちによるレジェンドマッチが中心部の仮設サッカー場で行われ、町の雰囲気が最高でした!試合当日は、スタジアム近くのパブで大型スクリーンで試合を観戦しました。
SMさん
カーディフ大学(Cardiff University)
平成28年8月~平成29年6月の月例報告より抜粋
9月
大学に関する近況
カーディフに到着したのが、9月14日でしたが、大学のオリエンテーションウィークは9月19日からでした。私の所属するMLANGのオリエンテーションは9月20日にあり、オリエンテーションでは履修に関して、テスト期間・長期休暇期間について説明を受けました。多くの人が、大学が始まる前にインターネットで履修を決定しており、私もその一人だったのですが、時間割はオリエンテーションの後に出ることになっており、時間割から考えて履修が不可能な科目があり、キャンセルしたい科目が出てきたのですが、一度履修を決定すると、簡単にキャンセルすることができず、担当者に直談判に行かなくてはならず、苦労しました。また、こちらの大学にはpersonal tutorという制度があり、一人一人に担当の先生がついてくださり、生徒が抱えているacademicな問題から、日常生活の問題までを最初に相談するsafety netのような先生がいます。・・・・・9月23日には、カーディフ大学で日本語を学び、日本に留学していた4年生の方と、日本の様々な大学からカーディフ大学に来た留学生が一堂に会して、交流しました。その日はその後、MLANG主催のwelcome wine receptionが行われ、MLANGに来ている各国の留学生たちとお酒を飲みながら、交流しました。授業は9月26日から始まりましたが、1コマ50分間の授業で、短いですが、その中でも生徒同士でdiscussionする時間が必ずあることや、生徒が分からないところを授業中にも積極的に質問に行くところが印象的です。また大学の1限は9:00からなのですが、1コマが短い分、コマ数が多く、私は21:00まで授業がある日があります。
個人の近況
まず、留学直前に苦労したことがありました。寮がいっぱいでは入れないとの連絡が、直前に来たので、大学側から勧められたCardiff UniversityのStudent Unionで紹介されたシェアハウスに入居する手続きに追われていました。シェアハウスは、光熱費は別なのですが、おそらく寮より安いと思われます。しかし、大学から徒歩20分くらいの距離にあることや、同じ方向に帰る人が少ないので、夜遅くに帰るときは少し怖いと感じています。シェアハウスの住人は他にイギリス人が2人で、たまに一緒に夕食を食べたりします。また、こちらに着いてからは、私は長距離バスを使ってヒースロー空港から、カーディフに移動したのですが、長距離バスの時間まで、meeting pointの椅子に座って、待っていると、知らないアジア系の人に迎えに来たことを装われ、話しかけられたのですが、外務省虎の巻で読んだ、トラブルのパターンと似ているということや、そもそも迎えを頼んでいたわけではなく、迎えが来るとも聞いていなかったので、騙されることなく、うまく対処できたと思いますが、本当にこうやって近づいてくる人がいるのだと実感し、空港に無駄に長居することは危険だなと思いました。また、後から思ったのですが、私はヒースロー空港に夕方着いて、そのままその日のうちにカーディフに移動したので、長距離バスを降りてから、家までタクシーを使って、夜22時ごろに到着しました。しかしながら、知らない土地で夜遅くに移動することは本当に危険なので、ホテルをとってロンドンに一泊すべきだったと思います。何もトラブルに巻き込まれなくて幸いでした。こちらには現地時間の14日夜に到着し、その日は寝るだけだったのですが、ベッドはあるが、掛布団がなく、困りました。他の寮に住んでいる友達に尋ねても、皆布団がなかったというので、これが普通のようです。このことを含めて、夜に到着することはあまりよくないと感じました。大学のオリエンテーションが始まるまでは、必需品を買い足すなどこちらの生活になれるのにいっぱいいっぱいでしたが、もう少し遅く到着してもよかったとも思いました。なぜなら一人で過ごす時間が長く、ホームシックに陥ってしまったからです。到着早々日本に帰りたくなりました。買い物は徒歩20分ほどのところに街の中心があり、ショッピングセンターの集まるアーケードがあるので、そこで何でも手に入ります。物価は思ったより高くなく、むしろ日本よりも安いと感じるものもたくさんあります。一例としてはパスタや、チーズが挙げられます。また、大学から徒歩10分ほどのところに、日本食スーパーもあり、普通のスーパーでは手に入らない、味噌やめんつゆなどを手に入れることができ、たいへん便利です。カーディフはコンパクトでまとまっている街ですが、観光スポットも多々あり、楽しく、住みやすい街だと感じています。こちらに来てから、周りに風邪をひいている人が多く、私も、喉と鼻をやられましたが、日本から持って行った薬と、早めの休養ですぐに治り、使い慣れた薬を持っていくことも大事だなと感じました。
10月
大学に関する近況
10月31日から1週間は、ほとんどの授業が、各々がこれまでの講義の復習を行う期間であるReading Weekのためお休みなので、12週間あるAutumn Semesterの半分の授業が終わりました。感想としては本当にあっという間で、少し焦ります。私の履修している授業のうち最も難しいと感じているのが、Managing Financeです。この授業では、現在簿記を学んでいます。日本でも簿記を学んだことがないので、英語でそれらの専門用語が出てくると理解をするまでに時間がかかってしまい、授業の復習も一苦労です。そういった意味ではこのReading Weekは落ち着いて復習に集中できるのでいい機会だと考えています。また、今一番興味のある授業はTranslationの授業ですが、ようやくSemminarが始まり、様々な言語に対応した一般的な講義を行うLectureとは違い、英語↔日本語の翻訳に特化した話が聞けるのが大変おもしろく、また少人数で意見を交わしやすい環境がとてもいいと感じています。例えば、交番に紛失物の届け出をした際、最後に「よろしくお願いします。」という時。これを英語ではどのように表現するのが適切かという課題が出ていたり、また、日本語の「お疲れ様です。」はどのように英語で表現するかということを授業内で考えたりしていますが、そのまま直訳できない部分に文化の違いや日本語の難しさを感じて興味深いです。
個人の近況
10月の初めに、ロンドンに旅行に行ってきました。カーディフでは手に入りにくい箸や、洗濯物干し、日本の調味料などを求めて、ジャパンセンターに買い物に行ったり、観光をしたりしてきました。ロンドンに向かう前にどこの地域の治安が心配か等、注意点を調べていきました。スリの被害が多いことを知り、心配していましたが、事前に調べて気を付けていたことで被害にあうこともなく、楽しく過ごすことができました。外国において、いかに気を抜かずに行動することが大切かを感じた一件でした。日々の生活面に関していえば、私はJapanese Societyという日本のサークルのようなものに所属しているのですが、毎週金曜日の夜にPubで集まりがあり、日本に興味があるカーディフ大学の学生や日本からの留学生と様々な話をして過ごしています。私は今のところ、このSocietyのみに所属しているので、友達の大半はこのSocietyのメンバーですが、皆専攻や出身も異なるので、様々な国の人といろいろな話ができることがとても楽しいです。また、卒業後に日本で英語を教えたいと言っている外国人の友達が多くいて、驚くとともに、日本に魅力を感じ、日本が好きだと言ってくれることをとても嬉しく感じました。Japanese SocietyはすごくアクティブなSocietyで、10月29日には、メンバーのお家でHalloween Partyをしました。とても多くの人が集まり、皆の仮装も本格的でした。夜遅くまで踊ったり話したり、本場でHalloweenを経験できたことがとても貴重だったと思います。10月最後のイベントとして、10月31日には、Societyの中でも特に仲良くしてくれる、中国人の友達が、アルバイトをしている中華料理屋さんに総勢10人でご飯を食べに行くことを企画してくれて、本物の中華料理をごちそうになりました。美味しい料理とともに様々な話やお店のカラオケで盛り上がり、とても楽しく有意義な時間を過ごすことができました。そのお礼として、11月には私の家に同じメンバーで集まって、鍋パーティーをする約束をしました。また、31日の夜には近所に住む子供たちが、お菓子をもらいにやってきました。日本からたくさん、日本のお菓子をもってきていたので、あげたところ、とても喜んでくれました。
11月
大学に関する近況
11月は全体として、テストや提出物のとても多い月で、授業もとても忙しい月となりました。特に、Specialised English Language Programmeという留学生向けに開講されているacademicな論文の書き方や、presentationの仕方などを学習する授業を履修しているのですが、以前の先生の体調不良により、新しい先生に代わりました。その先生がとても厳しく、毎週一週間での準備が大変な課題が出されるのですが、特に苦労したのは、group presentationの課題でした。即興で作られたグループで、先生がランダムに与えた国に関して観光案内をするという内容なのですが、専攻が様々かつ、その日初めて会話した人と、集まることのできる日を決めるだけでも一苦労でした。私のグループは、まず、授業後に最初の集まりの日程を決め、お題の国に関して各々調べてくるという約束をして解散しました。後日集まった際に、お題の国の調査結果をすり合わせ、発表のパートを決めて、各々原稿づくりを行いました。最後に発表当日の授業前に集まって時間を計りながら発表の練習をしました。発表では先生が時間ぴったりに発表を止めるので、もしも自分が長すぎると他のメンバーがせっかく用意したことを話せなくなってしまうし、時間が余り過ぎてもtime managementも点数になるので、減点されてしまうと必死で練習しました。結果、プレゼン本番は予定通りに進めることができ、最終的にもらったfeedbackもhigh markをとることができて、とてもいい勉強、そして経験になりました。・・・・・11月の一週目の月曜日から留学生向けのオプションの授業であるReading Strategyという授業を受け始めました。この授業では、academicな文章を効率的にかつ正確に読むにはどのようなことに注目したらよいかを中心に、単語の品詞の違いによって生じる微妙な意味の差異についてなど幅広く英語に関する知識を学ぶことのできる授業で、履修してよかったと感じています。また普段はあまり交流することのない専攻の違う人と交流することができることや、正規の授業に比べて人数が少ないゆえ、より参加型の授業で、discussionのしやすさが魅力だと思います。
個人の近況
11月は、街がクリスマスの準備をはじめ、カーディフにもクリスマスマーケットと移動遊園地がやってきました。11月の最初には、10月終わりに友達が中華料理をごちそうしてくれたお礼として、私の家で、鍋パーティーをしました。キムチ鍋を作ったのですが、皆が美味しいとたくさん食べてくれて、喜んでくれたのがとても嬉しかったです。また、11月は、イギリス国内に日帰りで旅行する機会がたくさんありました。カーディフ大学では、Student Unionがたくさんの旅行を企画し、長距離バスを手配してくれており、それが毎週末のように日帰りできる距離で、とても安い料金で開催されています。私は、友達の輪が広がればいいなとの思いで、一人で参加の申し込みをしました。11月13日にはBathに行きましたが、そこに偶然参加していたクラスメイトが私と一緒にまわってくれて、新しく仲良くなれた友達もできました。世界遺産のRoman Bathをはじめとして、Bathの建物はイギリスの他の地域の建物とはまた違った感じの街並みで、ローマにいるような気分になりました。・・・・また、翌週には同じくSUの企画を使って、Windsorにも行きました。Windsor castleには、エリザベス女王の生活している空間のミニチュア模型が展示されていたり、絵画、女王が過去の式典などで着ていた洋服の展示があったり、とてもおもしろかったです。また後から、授業で先生に聞いた話なのですが、Windsorのお城に国旗が掲げられている時は、その日はヴィクトリア宮殿ではなく、Windsorのお城に女王様が滞在しているということを意味しているそうです。あいにく、その日は旗が掲げられていなかったと思いますが、その知識を知ったとき、おもしろいなと思いました。そして、11月最後の旅行として、クラスメイトでマカオからの留学生の友達と、Bathのクリスマスマーケットに行ってきました。Bathのクリスマスマーケットはカーディフのものとは比べ物にならないほどに大規模で、多くの人が訪れていました。その光景を見て、ヨーロッパにおけるクリスマスの重要さとクリスマスマーケットがその準備として大きな役割を果たしていることを実感しました。・・・・11月は旅行以外にも、友達と近くのスタジアムにラグビーの日本代表vsウェールズ代表の試合を見に行きました。カーディフはラグビーの街と言われるだけあり、その日は朝からスタジアム近くの街の中心部は、応援に行く人々が、ウェールズの赤と緑のグッズを身に着け、はしゃいでいました。7万人ほど入る会場はほぼ満員で、とても接戦で、熱い試合でしたので、ヤジがたくさん飛んだりするのかなと少し不安だったのですが、ウェールズの人たちはとてもあたたかい人ばかりで、日本が得点を決めたとき、いいプレーをした時も拍手をするほどで、大変驚くとともに、とても楽しくいい気分で試合を観戦することができました。
1月
大学に関する近況
大学は1月9日からテスト期間でしたが、今期私は、テストがある授業を一つも履修していなかったので、この期間は、クリスマス休暇の延長のようなものでしたが、通年の授業を多くとっている私は、前学期の復習、また、1月に提出のessayなどのassessmentに追われていました。授業は、1月23日から始まりましたが、前学期の授業を受けて、履修の変更の手続きなどで1月はあっという間に終わってしまったという印象です。履修変更の手続きは、前学期に引き続き、receptionに問い合わせに行ったりして大変でしたが、前学期の経験が大いに役立ち、スムーズに行うことができました。今期履修している授業の中で今一番興味があるのは、Professional leadership and management skillsという授業です。実際に組織のリーダーとして活躍なさっていた講師の方が、case studyを交えて組織を率いていく上での重要なポイントについて話してくださいます。毎週21時までの授業で大変ですが、興味深いのであっという間に授業時間が過ぎると感じています。
2月
大学に関する近況
2月に入ってようやく履修が確定し、今期は前学期より多く授業をとっているため、勉強が前より忙しいという印象です。カーディフ大学では、1年間を通じて履修を組み、1年間に決められた単位をとるので、学期ごとの履修のバランスは本人次第です。私は前学期より今学期の方が授業を3つ多く履修しています。
また、今期は、自分自身のこちらでの生活にも、余裕が出てきたため、ランゲージパートナーに登録し、週におよそ3回、3人に1時間ほど日本語を教え、英語を教わる機会を作りました。自分の英語力の向上に役立っていると実感するとともに、日本語の難しさを感じる日々です。このランゲージパートナーという制度は、英語以外でも自分が履修している外国語を希望すれば、そのネイティブたちと言語交流をすることができます。また、カーディフ大学では、授業レベルがわけられていて、目に見えるように設定されているのですが、今回、レベルが標準より2段階ほど、高いのですが、どうしても興味があるNational Socialism and its legacyという授業を履修しました。授業内容はやはりとても難しく、ナチスドイツについて講義と議論、週3時間の授業です。やはりレベルの高い授業だけあって、周りの人たちはとても積極的で、毎回Seminarの授業では、熱い議論が交わされています。私は横国での履修上、こちらでフランス語を履修しなければならなくなり、フランス語を英語で学んでいます。elementaryというbeginarの次のレベルの授業をとったのですが、日本に比べてとても難しく感じます。
3月
大学に関する近況
今月は、assignmentの提出やプレゼン、クラステストなど、学期末に向けての大学の課題がたくさんありました。‥‥Managing Financeの授業が3月末で終わってしまいました。私以外の学生が皆社会人で、先生も留学生である私が、きちんとついてこれているかすごく気にかけてくださり、恵まれた環境で受けることのできた授業でした。2セメスター目は、簿記が多かった1セメスター目と異なり、ファイナンシャルアナリシスを中心に学び、それを応用して、ビジネスプランニングについても学びました。
4月
大学に関する近況
4月8日からイースター休暇になりました。その前に提出しなければならない課題がいくつかあり、忙しかったです。ついに留学先での授業が全て終わってしまい、残すはテストだけになりました。留学における授業を総括してみると、1学期目よりも2学期目の方が授業を多くとったということもありますが、生活に慣れてきて、いろいろな課外活動に参加したことや、就活もあいまって、時間が足りないと感じていました。
個人の近況
4月は早々に授業が終わってしまったので、大学の近況はあまりなかったのですが、個人としては、就活が大変忙しい月でした。4月15日・16日とロンドンキャリアフォーラムに参加しました。私は自分の行きたい業界に絞って、事前にエントリーシートを提出し、当日、履歴書を出して企業の面接を受けることはせず、事前に通っていた企業が2社あったので、その面接を受けに行く形でした。
AHさん
イーストアングリア大学(University of East Anglia)
平成28年8月~平成29年6月の月例報告より抜粋
9月
大学に関する近況
大学に到着してからすぐに、寮のカギの受領、BRPの受け取り、生徒登録を済ませました。これらの手続きは全てcongrigation hallという場所で一括して行われているので、地元の郵便局に行く必要もなく一度に終わらせることができました。26日から新学期が始まり、学部のもう一つ大きな括りであるArts&Humanityのレクチャーやパネルディスカッション、留学生対象の生活に関するオリエンテーションがありました。授業はほとんど2週目から始まるので、私はまだ1つの授業しか受けていません。その1つの授業は通訳の授業なのですが、英語、フランス語、スペイン語、日本語が対象なので1つの授業で全員がセミナーを受け、その後は言語別に実践的な授業を受けます。通訳者にとって必要な能力とは何かをインプットし、そこからは人の話を英語で一通り聞いた後、日本語で他の人に正確に伝える練習、同時通訳の練習、基本的なshadowingやdectationを練習します。この授業には日本人が私一人しかおらず、環境的にも授業の内容的にもすごく興味深くて役に立つなと感じました。それ以外では、English Learning Support Programという自分のmodule外の講座を取ることにしました。大学の環境については、緑に囲まれていて、充実したsportsparkもあり、大学中心には生徒によって経営されているカフェやバー、スーパーがあり、さらに書店、銀行、キャリアサービスセンターがありほとんど大学内で生活はやっていけます。学生も活発ですごく良い環境です。
個人の近況
私の寮のflatにはイギリス人が4人と留学生が2人住んでいるのですが、もう一人の留学生は英語が堪能で会話に全く支障はありません。みんなでキッチンに居るときも全員でわちゃわちゃおしゃべりしています。
その他
こちらの気候はだいたい15度くらいで朝夜は肌寒いです。もうコートを着るときもあります。ただ周りを見渡すと、ぶあついコートを着ている人もいれば半袖のTシャツを着ている人もいて、ファッションには特に気を遣わず、自分の着たいものを着ているという感じです。服に関してはcity centreのお店ではほとんど学生割引があってほとんど20%offくらいで買えます。他にも学生割引が利くお店がたくさんあったり、バスもyoung ticketで大学―city centre間の往復券で3£だったりと学生に優しい街です。ただやはり物価は高く、さらにレストランに入ると基本10ポンドくらいはするし、UEAの学生はほぼ毎日家でお酒を飲むかパブに行くのでそのお金がかかったりと、支出は多いです....。あと驚いたのは洗濯と乾燥で6£ほどかかります。すごく高いので1週間に一度枕カバーなどもまとめて洗濯するようにしています。
10月
大学に関する近況
授業数は日本にいるときより少ないですが、レクチャー、セミナーというイギリス式の授業形式はなかなか負担が大きく、毎日次のクラスへの準備に追われています。あと、先週からFormative assessmentという中間試験のようなものが始まり、私はその一環として、プレゼンテーションが2つとテストが6つあります。これらは特に成績に直接関係はなく、formativeの結果をもとに先生からフィードバックをもらって、最終試験のsummative asseessmentに向けて勉強するといった感じです。10月は特に変わったこともなく、毎週同じように授業を受けているだけなので、今回は大学の施設について書こうと思います。まず図書館が24時間空いていて、かつパソコンの動きは速いし、グループ向け、個人向けのstudyスペースが本当に充実していて、横国もこんな風だったらいいのにと思いました...。また、寮、IT関係、授業、お金、暮らし、SU(student union)のそれぞれに充実したサポートがあって、何か困ったことがあればオフィスに行くか、メールを送るかですぐに対応してくれます。また、イングリッシュバディーというシステムがあり、横国のチューター?と少し似ていて、アカデミックでない、普段の生活に必要な英語を教えてくれるなど、なんでも相談できます。私も先週からこのスキームが始まり、4年生の学生に担当してもらっています。
個人の近況
Dance square ROYALというダンスクラブに所属しました。春にある3つの大会に出るチームを作るためのオーディションがあって先週挑戦したところ、無事合格することができました。これからの練習と大会、そして新しい友達に会えるのが楽しみです。大会はノッティンガムやマンチェスターなどイギリス各地で開かれるので、そこへ行くのも楽しみです。フラットメイトとは1か月共に過ごして大分仲良くなりました。
その他
始めは英語の勉強のためにと思って始めた映画鑑賞にすっかりはまってしまい、1週間に3本は見るようになりました。はじめは英語字幕ありで見ていましたが、最近は字幕なしで見るようにしています。もちろん家で1人でフラットメイトとみることが多いですが、学校にcinema societyとDisney societyというサークルのようなものがあり、ここに参加して他の学生と映画を見たりもしています。
11月
大学に関する近況
11月は主にformative assessmentという中間試験のようなものがありました。Conference interpretingの授業では、simultaniousとconsectiveという二種類の通訳を実際にする、Advanced EnglishではIELTS形式のテストと一人10分のoral presentation、Beginners Frenchはwriting, listening, reading, speakingのテスト、Intercultural communicationでは男女不平等に関するdiscussionとpresentationがありました。どれも成績には関係ありませんが、試験の形式はしっかりしており各テスト後に先生からフィードバックをもらえます。・・・・・こちらのエッセイやプレゼンは日本以上にしっかりしているように感じます。例えば、referenceの引用の仕方から、ハーバードの決まりに沿った書き方、プレゼンテーションの構造の作り方、はじめにどういうことを述べてその後はこれを紹介して、、、といった感じに本当にきめ細かくガイドラインが指定されています。それに沿えばいいわけですから楽と言えば楽ですが、自分の意見やそれを支える証拠、より深い考えなどが求められるので大変です。また、11月は授業がすでにweek6に入ったこともあり、クラスのみんなの仲が深まりました。授業中の議論が活発になったのはもちろん、クラスの前後でおしゃべりしたり、授業時間以外に集まって勉強や課題を一緒にしたりしました。最後にキャンパスについてですが、クリスマスのデコレーションが始まりました。squareと呼ばれる広場のところにはおおきなツリーがおかれ、通学路や学校内の木々はたくさんのライトで灯されています。
その他
イーストアングリア大学はIELTSが6.0の時点で来られるけれど、できればやめたほうがいいなということです。・・・・きちんとIELTSをとって、イーストアングリアで自分の専攻、興味のある分野の勉学を深めることを強く勧めます。それほどしっかり勉強、議論ができる環境がこの大学には整っています。
12月
大学に関する近況
12月は主にsummativeといって最終試験がありました。私の場合は、フランス語、英語、通訳のテスト、英語のペアプレゼンテーション(環境問題についてですが、重要なのはoral speakingで、どれだけナチュラルに、わかりやすく、かつアカデミックな英語が使えるかどうかが大切)、Intercultual communicationという授業の個人プレゼンテーション(男女不平等について)と600字のself reflectiveエッセイ(以前のプレゼンテーションから、フィードバックをもらい自分でも改善して、summativeまでにどんな能力を向上させたかについて)がありました。自分のなかではきちんと勉強して臨み、うまくいったと感じています。・・・・・・学期が終わっても、学校の施設は基本空いているのですがクリスマス前から1月5日くらいまでは全てが閉まってしまいます。post roomといって郵便や荷物を預かってくれるところも閉まってしまうので少し不便です。(私は12月中旬に速達の飛行機便で日本から荷物を送ってもらったのですが、いまだに受け取れていないです)
個人の近況
春に受けようと思っている授業は、Advanced English, Construction of news, European Economics, Economics for business decision makingです。私生活については、12月ということでクリスマスのイベントに参加しました。Christmas ballといって、きちんとドレスアップして、イギリス式のクリスマスメニューを楽しむというものです。
その他
冬休みに入ってからヨーロッパ旅行に行ってきました。アムステルダム→ブリュッセル→ケルン→ルクセンブルク→パリという旅程です。・・・・・治安についても少し書いておこうと思います。とにかくヨーロッパはスリが多いです。以前旅行に行った友達にも、宿泊先のホストにも注意されました。私は肩掛けカバンをコートの中にかけて警戒していたので何も盗まれることはなかったのですが、ブリュッセルのまちを歩いていたとき、わたしがふと友達のほうにふりかえると、友達のすぐ後ろに男性がこちらをにらみながらぴったりとくっついていて危険でした。
1月
大学に関する近況
Spring semesterが始まって三週間がたちました。今学期は授業の濃さや課題の多さが前学期の比にならないくらいなのであっという間に時間が過ぎてしまいました。まず、Economics of business decision makingでは、経済的な観点というより心理学的観点から消費者の傾向をとらえてどうやって実際のビジネスに生かすかということについてレクチャーを受け、他のクラスメイトと話し合っています。2週間後にグループプレゼンがあり、私は4人のグループでVolkswagenのブランディング向上について調べています。最終的にはPower Pointを使った口頭でのプレゼンではなく、アニメーションや動画を使ったビデオを作って発表する予定です。European Economicsではグラフや理論を使って国家間レベルのマクロ・ミクロ経済の勉強をし、かつ現在一番重要な問題であるイギリスのEU離脱とからませて、実際の経済的影響を勉強しています。これも来週グループプレゼンテーションがあります。The construction of newsはメディア系の授業で、新聞やインターネット上の記事から、ニュースはどうやって出来事からニュースになるのか、記者はどうやってニュースを選択しているのか、各出版社によって特徴はあるかなどを研究しています。毎日たくさんのニュースをチェックしないといけないうえ、クラスは7人ほどしか生徒がおらず毎回たくさん発言せざるを得ません...。しかし私たちを常に取り囲んでいるメディアとはどういうものなのかを知れるので、大変興味深い授業です。これも2週間後にペアプレゼンテーションがあります。先にお題が4つほどだされていて、授業や毎日の自分の考察をもとに、自分のメディアに対する意見を発表するというものです。Advanced Englishは毎週3時間のセミナーがあり、毎回特定の分野について単語や表現の仕方、もちろんトピックについても学びながら、基本ずっと発言したり、グループで話し合ったりする形式の授業です。生徒が基本交換留学生や正規生だけどイギリス出身ではない生徒ばかりなので新しい文化を知れるし、友達もできました。先に述べたプレゼンテーションは基本全部20分間です。しかしこれは全部Formativeなので、これほど課題が重いにもかかわらず成績には入りません...。イギリスの大学生をしようと思ったら、本当にプレゼンなど人前で発表することになれないといけないと痛感しました。
個人の近況
1月はフィンランド、エストニア、チェコ、オーストリアを旅行しました。 ・・・・・学校では、私が所属しているダンスソサエティーが2,3月にロンドンでの大会を控えており、週に4回練習に励んでいます。・・・・ジャパンソサエティーがUEA Gloval:Europe, America and Asia というイベントでソーラン節を披露していました。踊ったのはジャパンソサエティーに所属しているUEA生徒と何人かの日本人留学生です。
3月
大学に関する近況
3月はThe construction of newsのプレゼンとEconomics of Business decision makingのエッセイがありました。
Newsのほうは、ニュースがイデオロジーをもってつくられているのか、純粋に事実を伝える媒体として機能しているかについて分析して発表しました。私は1つの特定の事件を3つの異なる新聞で読んで、伝え方の違い、含まれている情報の違い、言語の使い方などについて分析しました。客観的にニュースを見てみると、各新聞紙が明らかに独自の性格や政治的立場を持っていて、おもしろい発見の連続でした。
Business decision makingのエッセイテーマは、「Assess how behavioural economics can help us understand the consumer behaviour」というものでした。私は従来の経済学が主に数字やデータに注目し、消費者が理性的でprofit mazimizerであるという理論はあまり現実世界に当てはまらず、より正確に消費者行動を予測するには、広告によってどのように消費者が影響されるのかや、値段の書き方や周りの人の行動によって消費者の行動が変わることなど、心理学的なアプローチが必要で、その点でBehavioural economicsが有効であるという内容のエッセイを書きました。このエッセイは1500字で全然単語数は多くはないのですが、私はこの長さのエッセイを書くのが初めてだったため、構成の作り方やレフアレンスのしかた、読む人を説得できる自分の意見の書き方など、難しいことが多くありました。
個人の近況
3/11にDerby Day というUEA対Essexのスポーツ大会がありました。学校全体いろいろな場所で試合が開催され、お祭り騒ぎで楽しかったです。Squareという学校の中心の場所は、DJがいてお酒も売っていて、まるで音楽フェスのようでした。私はダンスの部門でJazzとHip-hopを踊りました。
その他
大学の友達が私に会いにロンドンに遊びに来てくれました。
4月
個人の近況
春休みにポーランド、スロバキア、ハンガリー、イタリアを旅行しました。・・・その後は、約2年前にエジンバラのサマーコースに参加したときにお世話になったホストファミリーに会いに行きました。
5月
大学に関する近況
5月ですべてのレクチャーとセミナーが終わり、テスト期間に入りました。私は最後の日(6/16)にヨーロピアンエコノミーのテストを控えていますが、多くの科目はエッセイの締め切りやテストがすでにあったりします。私はsummative assessmentとして、The construction of newsの授業でニュースを作る際の情報資源についてのプレゼンテーションをしたのと、新しいコミュニケーションテクノロジー(インターネット、SNSなど)がこれまでのニュースの特徴にどのように影響するか、またこれから先の新聞業界へどのように影響するかというテーマで2500字のエッセイを書きました。Economics of business decision makingの授業では、すでにビデオプレゼンとBehavioural economics(行動・心理経済のようなもの)についてエッセイを書いていたので、最後は今まで学んだ理論をどのように実世界に活用するかというレポートを書きました。私はターゲット会社としてTOSHIBAを選んで書きました(3000字)。
‥‥テスト期間、エッセイの締め切り前ということで図書館は毎日大混雑です。朝早く行って席を確保してそのまま夜までずっと勉強という生活を送っていました。でも図書館だけではなくて、最近天気が良くとても暖かいので、外で勉強している人も良く見かけます。自然が多いUEAならではだなと思いました。
個人の近況
UEAの卒業生が主に主催してくださった、KPMGとBarclaysのロンドンオフィス訪問に参加しました。申し込みの方法は、UEAのCareer Central を通してCVとなぜこのイベントに参加したいかなどの理由を書いて提出し、選考されるという形でした。これは全学部の1、2年生向けで、当日は法律、ビジネス、経済、心理学などいろいろな学部から30人ほどが来ていました。
その他
5月7日にUEAキャンパス内のLCRというクラブで、Dance showという私にとって最後のダンスのイベントがありました。振り返ってみれば10月にオーディションを受けてから約7か月間、Royal(ダンスチームの名前)としてメンバーみんなと踊ってきました。長かったような短かったような、、、。私の留学生活はダンスのおかげでさらに充実したものになりました。
YNさん
オスナブリュック大学(University of Osnabrück)
平成28年8月~平成29年6月の月例報告より抜粋
10月
大学に関する近況
10月12日からウェルカムウィークがあリ、様々な手続きをしました。その期間中に履修登録、住民登録、ドイツの健康保険の加入、ドイツの銀行開設の手続きを終えました。そして10月24日から授業が始まりました。私は現在履修している授業は、10ETCS分のミクロ経済学(2 Lectures + 1 Tutorial + 1 Excersise )とドイツ語の授業が週に2回合計8時間です。そのほかにもドイツ語で授業を聴講する予定です。
個人の近況 私は現在住んでいる大学寮のフロアリーダーになりました。業務内容は11月3日の会議によって分かります。そして大学の部活に参加しようと思ったら定員割れしてしまい、参加することができませんでした。オスナブリュック市内にあるクラブなどにも問い合わせてみます。ほかにもできればインターンやボランティア活動を積極的にしたいので、問い合わせる予定です。
その他
オスナブリュックの夏は短く、10月初頭から寒さを感じるようになりました。今は朝の7時に起きても外は真っ暗です。そして夕方の5時ぐらいから外は薄暗くなっています。そして週に一回以上は雨が降ります。
11月
大学に関する近況
ドイツ語の授業は思ったより進行が遅いです。ドイツ語を話せるようになって帰国するには、独自に勉強を重ねて、常にドイツ文化とドイツ人と触れ合う必要があると感じます。・・・・・経済の授業はミクロ経済だけに絞ることにしました。ミクロ経済を教えている教授がイギリス人で、聞き取りやすく、わかりやすく、内容も吸収しやすいです。
個人の近況
20人でシェアする学生寮はマネージメントも大変です。私は寮のフロアリーダーになってから様々なことに気がつくようになりました。例えば、食事をする時間、シャワーする時間、使用する調味料、掃除をする習慣が文化によって違ったり、性格によって違ったり、様々です。最近キッチンで使用したものを片付けない人が増えてきました。これは国籍によらず、文化によらず、各個人の習慣の違いや家庭環境の違いから生まれたものだと考えています。今月から掃除当番を作り、実施をしましたが成果はイマイチです。どのようにして効率よく20人が住む寮の共有スペースを快適に使用するかについての問題はフロアリーダーとして大きな課題です。
その他
最近自分の寮で強盗事件が発生しています。すでに同じフロアに住む二人のパソコンが盗まれるという事件が発生しています。
12月
大学に関する近況
11月末からドイツ各都市にクリスマスマーケットが設置され、ドイツの厳しい寒さを吹き飛ばすかのような賑やかさが町の中心部に散漫していました。・・・・大学は17日から冬休みに入り、ヨーロッパ各地からエラスマスプログラムで来ている留学生は実家に帰りクリスマスを過ごし、アジア圏やアメリカ大陸から来た留学生はヨーロッパを周遊したり、ドイツのクリスマスを満喫したりしている様子が見られました。
個人に関する近況
12月の半分は大学の授業に専念し、半分は母親と旅行していました。母と一緒にデュッセルドルフ、オスナブリュック、ハンブルク、ブレーメン、オーストリアの首都ウィーンに行きました。旅行期間中改めてドイツ語を学んでいてよかったなと感じさせられた場面がいくつかもありました。
その他
ベルリンのクリスマスマーケットがトラックに突っ込まれて12人を死亡させて事件があったとき、ちょうど私もベルリンにいました。幸運なところにその夜私は疲れていて外出をしませんでした。人込みのあるところはなるべく避けながら残りの留学生活を過ごしたいと思っています。
2月
大学に関する近況
2月に授業はなく、ずっと試験期間でした。試験期間以外の日々は試験のための勉強に費やす日々でした。半年の期間を利用して留学してきた学生はほとんと母国へ帰りました。次の学期が始まるのは4月3日からです。それまでは授業もなく、休み期間です。
個人の近況
私は試験が2月の初旬に終わり、2月10日に新しく快適な寮へ引っ越しました。その新しい寮に2人ドイツ人の大学生と私と3人で現在暮らしています。もう一つ空き部屋があるのできっと4月になったらもう一人留学生が来ると想います。そのうちの一人のドイツ人は私と同じく経済学を勉強しています。来学期から勉強仲間がいると思うとなんだか心強いです。ドイツの経済などについてたくさん話せる機会があることにとってもワクワクしています。
その他
2月25日土曜日に開いてるはずのお店がほとんど閉まっていました。その原因を探るために歩き回ってみたところ、新しい寮の前にある大通りから爆音と仮装している人々を見つけました。その日はケルン発祥のカーニバルでオスナブリュック市全体の老若男女で祝っていました。
2月
大学に関する近況
2月に授業はなく、ずっと試験期間でした。試験期間以外の日々は試験のための勉強に費やす日々でした。半年の期間を利用して留学してきた学生はほとんと母国へ帰りました。
個人の近況
私は試験が2月の初旬に終わり、2月10日に新しく快適な寮へ引っ越しました。その新しい寮に2人ドイツ人の大学生と私と3人で現在暮らしています。もう一つ空き部屋があるのできっと4月になったらもう一人留学生が来ると想います。そのうちの一人のドイツ人は私と同じく経済学を勉強しています。
その他
2月25日土曜日に開いてるはずのお店がほとんど閉まっていました。その原因を探るために歩き回ってみたところ、新しい寮の前にある大通りから爆音と仮装している人々を見つけました。その日はケルン発祥のカーニバルでオスナブリュック市全体の老若男女で祝っていました。
3月
大学に関する近況
3月中はずっと春休み期間でした。
個人の近況
私は、3月6日から3月30日にかけてドレスデン工科大学のドイツ語語学研修に参加していました。その間ずっとドイツ語の勉強に没頭し、日常でもなるべくドイツ語を使ってクラスメートの人たちと会話をしていました。
5月
大学に関する近況
天気もすっかり晴れてきて、気温も暖かくなってきました。学生たちは大学の前にあるシュロスガーデンで友達とビールを飲んだり、フンキーボールで遊んだり、読書をしていたりするのが見れます。
KTさん
セントイシュトヴァーン大学(Szent István University)
平成28年8月~平成29年6月の月例報告より抜粋
9月分
大学に関する近況
セミスター開始すぐということもあり、様々なイベントが開催されています。いくつかに出席しましたが、日本を紹介する機会があったり、他の国について知る機会があったりと、かなり充実していました。
個人の近況
自分の所属しているコースは、ほとんどがヨーロッパ諸国からの留学生の一方で、日本人は1人だけということもあり、その雰囲気に圧倒されています。
10月
大学に関する近況
授業が本格的に始まり、1週間の生活リズムがある程度できてきました。授業自体は基本的な内容のものが多いので、ついていくのに苦労するということはあまりありません。
12月
大学に関する近況
昨日、今学期履修していた授業の試験・プレゼンテーション等が全て終わりました。試験自体は基本的な内容を問うものが多く、勉強不足で解答できないということはほとんどありませんでした。・・・・・授業内容はかなりベーシックなものが多いです。
1月
大学に関する近況
12月中に全ての授業、試験、プレゼンテーション等が終わっていたので、1月は講義棟内に行くことはなかった。クリスマスから年末年始にかけては、多くの留学生、現地学生が実家に帰ったため、寮内も閑散としていた。留学生を支援する団体のイベント等もなく、ハンガリーに来てから最も時間に余裕のある月であった。
3月
大学に関する近況
春学期が始まって2カ月が過ぎ、授業の内容も本格的になってきました。先月の報告書でも触れたとおり、今学期は良い先生にも巡り会え、授業におおよそ満足しています。今学期は、横国で学んでいる経済学ではなく、今まであまり学んでこなかったビジネスに重点を置いた授業を中心に履修しているため、かなり難易度が高く感じます。いくつかの授業では中間試験や中間レポートがあり、先週・今週あたりはそれらに追われています。
個人の近況
日本では就職活動が本格化し、かなり焦りを感じるようになってきました。‥‥来週末のロンドンキャリアフォーラムに向けて、事前の書類作成やウェブテストなどを行っているところです。
その他
4月に入り、一気に暖かくなってきました。冬がとても寒いこと・街に緑が多いことから、こちらの春は日本以上に気持ちよく感じます。最近は週末に公園にでかけてのんびりしたり、授業後に友達とスポーツをすることもあります。
4月
大学に関する近況
いよいよ授業も佳境に入りつつあり、いくつかの授業では中間試験・エッセイの提出がありました。5月になると最終試験・最終課題が控えているので、計画立てて勉強を進めていきたいと思います。また、授業とは関係のない特別講義が2回開かれ、偶然にもどちらも「日本の技術力とハンガリーのビジネス」がテーマでした。
個人の近況
4月はハンガリーに来てから最も忙しい月でした。上記の通り、試験や課題提出が続いただけでなく、就職活動に関連してロンドンキャリアフォーラムへの準備に多くの時間を割きました。
その他
いよいよ帰国時期が近づいてきたと実感があります。先日、航空券を購入し、6月13日の帰国を予定しています。
YKさん
オタゴ大学(University of Otago)
平成29年2月~平成29年12月の月例報告
2月
大学に関する近況
2月初めから2週間、交換留学生を対象としたフリーコースに参加しました。コースは概ね9時から12時で終わりましたが、Library, Information Center, Student Health Center, International Office等の重要な施設の場所を実際に訪れ、提供されているサービスとその利用方法の説明を受けたり、先生のおすすめな大学近隣のスーパーマーケット・八百屋等の場所やオタゴの主要な通りを聞いたり、New Zealand Englishの特徴について学んだりした他、会話を弾ませるためにはGDFC(General, Detail, Feeling, Conclusion)が必要なこと、大学にはhisやherの代わりにtheirを使う等、性別を明らかせずに曖昧に隠す方針があることなど、学術的な事柄も学びました。最終日の前の日には、先生の運転でCity Tourにも連れていってもらいました。家庭学習としてSummaryの練習も行い、最終日には各国の文化についてのプレゼンテーションを3-5分間行いました。
2月3週目はOrientation Weekとして、International StudentのためのOrientation SeminarやOfficial Welcome等のさまざまなイベントがありました。Club Dayでは、私はOUTA(Otago University Tennis Association)にSign upしました。スポーツ系のクラブは入会自体が無料のようです。日本クラブ・日本人クラブの類はありませんでした。
最終週からとうとう講義が始まりました。私は予定通り、Micro Economics, Maori Society, Comparative Politicsの授業を受けています。
個人の近況
コースは当初5人で始まり、途中参加者を含めても最終的に10人という少人数でした。5人がヨーロッパ人、そこそこ英語の話せるブラジル人と韓国人、なかなか会話に参加できない中国人と日本人2人といったメンバーで、専門や学年もさまざまですが、コース終了後も交流が続いています。
フラットメイトはニュージーランド人の3年生の学生(Kiwi Host)とカナダとアメリカからの交換留学生です。みなネイティヴなのでKiwi Hostの友達たちともすぐになじんでいたりともちろん疎外感はありますが、彼女たちはその分余裕もあるので頼りにはなっています。Kiwi Hostが車を持っているので、皆でビーチに行ったりglow warmを見に行ったりしました。
日本でも実家を離れて寮暮らしや一人暮らしをしたことがなかったのですが、洗濯は乾燥機で干す手間もなく、キッチンにも大体のものが揃っているし、部屋には十分な大きさの勉強机とたんす、クローゼットがあり、ベッドがダブルなので広々と寝られて、また、私のフラットは偶然シャワールームとトイレが別の部屋に分かれていることもあって、フラットは住み心地がいいです。食事は基本的に個々で作って食べていますが、自分で作れば日本で食べていたようなものを外食をしなくても食べることができるのでいいと思います。
その他
文房具・食品などにかかる金額は明らかに日本より高いと感じますが、意外なものがとても割安なこともあり、容量も多いので、一概には言えないところです。晴れていると日差しは強いですが、気温は日本の夏ほど高くなく、常に長袖を羽織っています。天気が変わりやすく、1日の中に四季があると言われるくらいなので、朝は寒いです。とは言っても、今は夏なので、21時過ぎまで日が出ていて驚きました。
3月
大学に関する近況
2月と変わらず、Micro Economics, Maori Society, Comparative Politicsの3つの授業を受けています。Micro Economics以外の2つは100 levelなので、Lecture Recordingというシステムで講義終了後に見聞きし直すことができます。Micro Economicsでは、はじめのうちは市場均衡などの日本で既に習ったことをやっていたはずが、予期していなかった行動経済学などを扱い始めたときには、これはミクロ経済学なのかとかなり焦りましたが、Weekly Test(選択式)はそれなりにでき、何とか理解できたのではないかと思っています。Turorialでは、講義で扱った理論などを現実社会に適用したりうまく適用できない理由を考えたりととても興味深いです。が、Tutorial後にその難題を自分で考え英語の文章にして毎週提出しなければならず、講義のレジュメの表現を必死に応用して書いているので、記述式の期末試験が不安になっているところです。
Maori Societyではこちらに来て1回目の大きな課題として1500wordsのエッセイにも取り組みました。3冊以上の参考文献を読み、日本で書いていたものより長くアカデミックなものを書くということに加え、書きあがったWordファイルが提出のシステムに拒否されるなど、最後まで大変でしたが、Paper Administrator(オタゴではコースのことをpaperと呼びます)の先生とやり取りしたり、Student Learning Developmentという留学生だけでなく全学生の学習をサポートしているようなところに質問に行ったりWorkshopに参加したりと、サポートがしっかりしているので無事終わりました。
個人の近況
Flatで、毎週日曜日の夕食を順番に誰かが作り皆で食べるという制度が始まりました。私は一応日本のものを作った方がいいのかと思い、いくつか挙げた候補の中で美味しそうと言われたカレーライスを、豚肉の薄切りがないのでチキンで作りました。次に人気があったのがうどんだったので、次回どのようにしようかと考えています。
それ以外にも、Kiwi Hostが出かける場所を提案してくれた週末にはみなで出かけていて、Botanic GardenやBaldwin Streetに散歩へ行ったり、SPEIGHTSというビールメーカーのブルワリー見学に行ったりしました。
また、Language Mentorという制度を知り申し込んだところ、倫理学専攻のKiwiの学生が私の担当に決まり、毎週金曜日に1時間話す機会ができました。
その他
気がつくと日没も20時前になり、紅葉や落葉も見られ、秋になったのを感じます。朝晩はかなり寒いですが、部屋のヒーターはある程度の時間で勝手に切れてしまうのが難点です。通り雨が多く、折り畳み傘が軽く折れてしまったのと傘を差している人が本当に少ないので、レイン・ジャケットを買いました。
4月
大学関する近況
今月は14日(金)から25日(火)までの間、大学が休みだったので、取り立てて先月からの変化はありませんが、4月はじめと5月はじめに大きな課題が合わせて3つあり、Mid-semster break以外の時間の大部分をそれらに費やすことになりました。Maori StudyのLong Essayに取り組んでいた際には、鞄や飲食物の持ち込み禁止で書架から自分で文献を取れない特別な図書館も利用し、ニュージーランドでマオリに関する授業を取ったからこその経験ができたと思います。
個人の近況
周囲にはキリスト教徒をほとんど見かけませんが、Good Friday、Easter、Easter Mondayと土曜日を除いて連日の祝日の間を、大学やスーパーなどがきちんと閉まっていて、外国らしさを実感しました。Easterにはhot cross bun、ANZAC DayにはANZAC CookieをKiwi Hostが作ってくれました。
その他
日本人以外の交換留学生は半期での留学なので、帰国が近づいているという話をだんだんとするようになってきました。
5月
大学に関する近況
4月の報告書にも少し書いていた通り、今月はじめにMaori StudyとComparative PoliticsのEssay課題がありました。Maori Studyの方は冠詞の有無等の文法のエラーが増えたことなどもあり、第1回目のエッセイよりも評価が下がってしまいましたが、Comparative Politicsの方は中国の全国人民代表大会に関する興味深い参考文献を見つけたことが功を奏して8割弱の評価をもらうことができ、素直にとても嬉しかったと同時に、英語のネイティヴでなくても結果は出るという今後への励みになりました。
個人の近況
今年で123回目となる毎年恒例のCapping Showという"ブラックジョークをふんだんに盛り込んだ、劇・映像編集・楽器演奏・歌・メイク等々の全てを学生が行う何本ものショート・コメディーのようなものの集まり"をKiwi Hostがチケットを取ってくれて、Flatのみなで観に行きました。
その他
日没が18時前になり、最低気温が5℃以下、最高気温が10℃以下になることも多くなってきました。歩いているときに見える丘の頂には雪が積もり、まだ秋なことが信じがたいです。
STさん
マッコーリ大学(Macquarie University)
平成29年2月~平成29年12月の月例報告より抜粋
2月
大学に関する近況
2/20からOrientation weekがはじまりました。初日にExchange welcomeがあり、交換留学生は欧米からの留学生が多いように感じました。外にはカラフルなテントが並んでいて、いろいろな団体が新入生の勧誘を行っていますが、自分から参加したい団体のテントに出向く形式です。銀行や通信会社など企業のテントもいくつかありました。また、新入生向けにreferencesの書き方等様々な講座が開催されていて、留学生としても助かります。また、student connect というわからないことを何でも質問できるところもあり、とても親切な大学だと思います。
履修登録はオンラインで1月中旬から授業開始2週目まででき、1セメスターあたり3~4つのUnitを履修します。交換留学生は1年生向けの100番台の授業はほとんど履修可能で、2年生以上向けの授業は成績証明書を添付してwaiver申請を行い、許可されると履修できます。こちらもすべてオンライン申請します。授業内容についてはオンラインのUnit Guideで確認でき、YNUと同様のシラバスに加え、課題の内容や提出日まですべて書かれています。
私は"English as a foreign language (EFLA100)","Academic communication in Business and Economics (ACBE100)", "Macroeconomics Principles (ECON110)", "Business Statistics (STAT150)"の4つのUnitを履修することにしました。すべてのクラスが大人数で行うLectureと2~30人で行うTutorialで構成されています。1週目が終わり、Lectureはそれぞれ授業の概要と導入程度だったのですが、今のところ特に難しそうと感じるものはありませんでした。Tutorialは自己紹介と簡単なDiscussion等の授業が多かったです。また、ilearnというYNUの授業支援システムのようなものがあり、そこでは授業資料や課題提出に加え、学生同士が情報交換しあうDiscussion Forum という場が設けられているなど、ITサービスがとても充実しています。
個人の近況
2/16午前にシドニー空港に到着しました。驚いたことに飛行機の隣の席がMacquarieに交換留学する他大学の学生でした。大学の無料送迎サービスを利用して寮に着きました。大学内にはお店や病院があり、さらに大きなショッピングモールが隣接しているので生活には困らない環境です。いろいろな国の料理のレストランがあり、歩いている人の話している言語も様々で、多文化国家を実感します。ラーメン屋や寿司屋等日本食レストランもたくさんありますが、価格は日本の2.5倍くらいです。寮は5人で一軒のシェアハウスのようなところで、ルームメイトは現地の学生と、カナダ、アメリカからの交換留学生、中国からのフルタイム留学生です。現在多くの団体で新入生歓迎イベントが開催されていて、私はExchange Students Society(MACex)とJapanese Association(JAM)のイベントに参加し、どちらも無料でピザと飲み物がふるまわれました。JAMのイベントにはMacquarieの語学学校に通う日本人学生も参加していて、普段はほとんど見ない日本人が過半数を占めていたのがなんとなく不思議な感じでした。‥‥日本語学科の先生に協力していただいて、こちらの日本語学科の学生数人とLanguage Exchangeを始めました。
その他
到着当初は晴れて暑い日が続いていましたが、2月下旬から突然の豪雨が降る日が多く、涼しくなってきました。日本では見慣れない様々な鳥や動物がキャンパス内で多く見られて面白いです。
3月
大学に関する近況
3月に入り本格的に授業が始まりました。Lectureは日本の大学のような、大人数の講義形式で行われ、すべての先生がスライドを使って講義をしています。ilecuture受講もできるので、基本的に希望者は全員履修登録できます。レジュメをilearnというサイトからダウンロード可能で、さらに講義後にはEchoというシステムを使ってオンラインで講義を視聴できます。これらを利用して授業中に聞き取れなかったところやメモを取り逃したところを確認できるので、とても助かっています。Lectureを受けていて、授業中に気になったところをその場で手を挙げて質問する学生が多くいるところは日本と大きく異なっていると感じます。
Tutorialは少人数でゼミのような形式で行われ、どのUnitも毎週宿題の答えあわせや、記事等に関するDiscussionを行っています。こちらは基本的に出席が義務付けられています。経済系のUnitはほとんどがオーストラリアの学生で当初はかなり緊張していましたが、課題がこなせているおかげでグループワークになんとか参加できています。課題は今のところ思っていたよりは多くなく、順調にこなせています。どの課題も形式等が細かく定められていて、ほとんどの課題はオンラインで提出し、Similarityがチェックされ規定を超えていると再提出になるので、期限に余裕をもって提出する必要があります。剽窃に関しては参考文献の書き方も決まりがあり、剽窃についてはかなり厳しいです。また、CommerceのUnitは日頃の課題が少ない分Final Examが重要らしいので、しっかりと準備して臨もうと思います。クラス内に日本人留学生がいない分、日本の話題の時には意見を求められることがあるので、もっと勉強が必要だと日々感じています。出発前にいろいろな方から言われていたことですが、やはり日本語での知識があればあるほど、英語での理解がしやすいように思います。
個人の近況
週末はオペラハウスやハーバーブリッジ等、Cityの観光に行きました。シドニーの電車はOpal cardという交通電子マネーを利用すると日曜日はどれだけ移動しても一定額までしか料金がかからないらしいです。食事については外食が高く、時間にも余裕があるので、なるべく自炊をしています。スーパーでは野菜や肉類がkg表示で売られているので、一見高そうに感じますが、実際日本よりも安く売られているものも結構あります。そして量を多く買えば買うほど安くなります。また、様々な国の食材や調味料を買うことができ、多文化国家を実感します(ただ、本当の日本の製品とは少し違います)。近くのショッピングセンターにアジアンスーパーもあるので、割高ではありますが日本製の調味料も手に入ります。
その他
通常シドニーではこの時期あまり雨は降らないそうなのですが、今月は雨の日が多かったです。雨が降っているときは半そででは少し肌寒く感じます。しかし晴れているときはとても暑いので、体調管理に気を付けなければと思います。
SSさん
シドニー工科大学(University of Technology, Sydney)
平成29年2月~平成29年12月の月例報告より抜粋
2月
大学に関する近況
大学に関してはまだ始まっていないので授業の事は話す事はできないが、簡潔に大学、寮、その他について述べたいと思う。
大学自体はシドニーのちょうど中心にあり、シドニー中央駅からも非常に近く交通の便は非常に良い。寮はBlugaという大学から徒歩10分ほどのところにある。家賃は高い。寮が留学生向けにイベントを日々開催しているので、それに参加する事で色々な人と会う事が出来る。また、大きなスーパーマーケットもあるので、生活にも大きな不便は存在しないと考えられる。
気候については非常に天気が変わりやすく、毎日晴れ、曇り、雨の全てを必ず経験しているほどである。傘を持っていないで急に雨に降られても雨宿りすれば少し後には止む事が多い。
物価は外食は高いが、スーパーで買う分には日本より安いと感じた。ただ、外食に関しても量が多いので値段相応であると感じる。日本の食材を売っているスーパーもあるので、食事が合わないということもなさそうである。現金は普段ほとんど使わず、基本はカード決済になっている。英語はオーストラリア訛りというほど現地の若い学生は訛っていないように感じられる。最初の一週間を通して比較的留学のしやすい国、大学であると感じた。
個人の近況
寮の同じ部屋の人と仲良くなることができ、大学のイベントで一緒に行動したり一緒に映画を見たりしている。しかし、コミュニケーションをとるのは大変で、特にドイツ人の友人の訛りがきつくほとんど何を言っているかわからない。うまい具合に相槌を打ってなんとか対応している。会話に関しても自分があまり長く話すことができないので、相手が主に話し、そこに自分が短く疑問などを返す形が多い。日本人とも何人か仲良くなり、外国の留学生と日本人何人かで一緒に日本のカレーを作って食べて交流をしたりした。また一緒にいった横国の友人ともコミュニケーションをとるようにしている。海外に何度も言っているため、大きなカルチャーショックはないがやはり日本のように察する文化ではなくしっかり主張しなければいけない文化であると感じている。
3月
大学に関する近況
大学では3月の終盤から授業が始まった。正規の学部の授業ではないため、英語力そのものの向上とオーストラリアへの理解を目的とした授業である。出される課題もあまり難しいものではなく、比較的取り組みやすいものになっている。そのため、よくも悪くも自由時間は非常に多い。・・・・バディプログラムと呼ばれる留学生にたいして現地の学生がバディとして色々会話してくれるボランティアのプログラムがあるので、それを利用して毎週1時間ほど学生と一対一で会話をしている。
5月
大学に関する近況
大学の授業では6月の最終レポートに向け様々な課題が出た。例えばオーストラリアで働いている人にインタビューを行い、その内容をプレゼンしたり、オーストラリア映画を見てそれについてのプレゼンを行ったりした。
その他
EPSON Australiaでインターンを行わせてもらえることになった。
KSさん
シドニー工科大学(University of Technology, Sydney)
平成29年2月~平成29年12月の月例報告より抜粋
2月
大学に関する近況
まだ本格的にオリエンテーションは始まっておらず、UTS Welcomeという入学式のような大学生活における注意や、アボリジニのセッションや、今後のキャリアについて講演、Giving a presentationというプレゼンの仕方についての講演を受けるだけでした。
3月
大学に関する近況
大学のオリエンテーションが終わり、授業が始まりました。私は、Australian Language and Culture Studies program という学部準備コースに今学期は所属しています。授業や課題は、他の正規の学部の授業と異なり、大変ということは感じません。むしろ、同じコースの中で日本語を話すことができないのは1人だけという、ほぼ日本人のためのコースです。先生の話す英語も、現地の学生ほど早くなく、学生のレベルに合わせていると感じました。授業の時間は、3時間ですが、グループワークなどのアウトプットの方が多いうえ、途中に休憩時間もあるので、退屈には感じません。課題をこなしつつ、HELPSという授業外の英語サポートプログラムに参加しています。Writingの添削や、会話練習の場として利用しています。特に、バディプログラムという1対1で地元の学生と話すものが、比較的人見知りの自分には非常にありがたく感じています。 このセメスターでは、授業・HELPS・IELTSの試験対策(自習)をうまく両立させながら、IELTSの要求スコアを超えて、次学期の正規の学部授業に備えることが目標になりそうです。
その他
大学では、週に2日無料の朝食が出ていたり、週に1日無料の夕食用にヌードルのフォーが出ていたり、大学内に設定されているパソコンの多さなどに、驚かされます。特に、日本でいうサークルの合同新歓のイベントには、無料のホットドッグ、バッグ、モバイルバッテリーなど様々なものが配られていました。
4月
大学に関する近況
先月に引き続き、HELPS・授業・IELTSをうまく使いながら勉強しています。IELTSの試験が近いこともあり、HELPSのバディプログラムでスピーキングセクションの練習の手伝いをしてもらっています。
個人の近況
4月の初めに寮対抗のスポーツ大会がありました。自分はフットサルに参加しました。自分の寮の人と中を深める良い機会でした。stu vacという学期の中間休みを利用し、ケアンズへ旅行したり、日本で知り合っていたオーストラリアの人と会ったりしました。
その他
ケアンズ滞在中に携帯電話を故障させてしまいました。・・・・・幸いsimカードは機能するので、機体購入だけすれば日常生活には支障ありませんでした。
5月
大学に関する近況
自分の所属しているコースももう残り1,2周となりました。3科目中2科目の成績は基本的に授業中のプレゼン、課題としてのレポートをもとに評価され、自分は各クラスであと1つずつレポートを提出すれば終わりです。残りの1科目に関しては、最後のクラスで行われるIELTS形式のテストで成績が決まります。